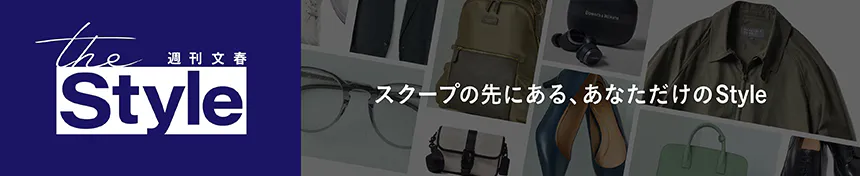第2次世界大戦における旧日本軍のもっとも無謀な作戦であった「インパール作戦」。インパール作戦に従軍した兵士たちが戦後に抱いていた、涙と怒りの感情とは?
ここでは、ノンフィクション作家・保阪正康さんの著書『昭和陸軍の研究 下』(朝日文庫)より、一部を抜粋して紹介する。(全2回の2回目/1回目から続く)
◆◆◆
将兵の恨みの矛先は敵軍ではなく…
インパール作戦に関する著書は、私の調べでは、これまでに30冊ほどが刊行されている。むろん私家版も含めると100冊をはるかに超えるであろう。そのなかでもっとも早い時期に公刊されたのは、昭和31年(1956年)10月の『インパール作戦の真相』である。
著者はインパール作戦に従軍した将校の音田福松だが、音田は兵員輸送の任にあたっていたため、あまりにも多くの悲劇をみてしまったらしい。それを書き残しておかなければという使命感にとらわれての刊行と、序文でも書いている。この書のなかには、次のような表現がなんどもでてくる。
「西北ビルマの印緬国境の山岳地帯に白骨を晒(さら)し、あるいはチンドウィン河の藻屑(もくず)となった数万の英霊は、無縁仏として今なお、あの恐怖のチンドウィン河岸地区のジャングル地帯を、徘徊し続けていることであろう」
「戦場余す所なく、蟻のはい出る隙もない位に目を光らせて乱舞し、樹木すれすれの超低空で猶々(ママ)と翼を伸ばして攻撃して来る敵機の翼下で、戦った各部隊将兵の精神不安はまことに想像以上で、5尺の身の置きどころさえなく、その上半年も降り続く雨の中や、南ビルマの大湿地帯をマラリヤ・アミーバ赤痢、ビルマかいように悩まされ、栄養失調の身となって、宿るに家なく食うに糧なく、敵機の目を避けるため、全軍終戦まで夜間行動をよぎなくされた。これでは如何に大和魂を誇る頑健な日本軍将兵も、心身共に完全に参らざるを得ないであろう」
これに類する表現にであっているうちに、インパール作戦に従軍し、辛うじて生存して帰還できた将兵は終生この記憶から逃れることはできないだろうと思えてくる。