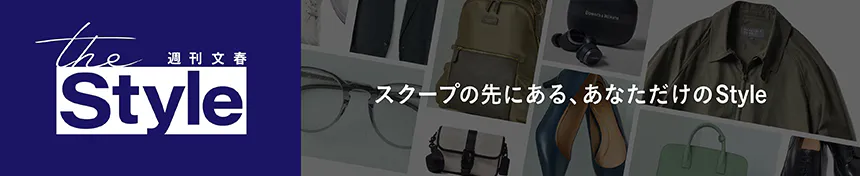貫井徳郎の六冊目の短篇集『紙の梟 ハーシュソサエティ』は、二〇二二年七月に文藝春秋からハードカバーで上梓された。本書はその文庫版である。
初見の方のために紹介すると、貫井徳郎は一九六八年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒。第四回鮎川哲也賞の最終候補作『慟哭』で九三年にデビュー。同作は九九年に文庫化され、六十万部を超えるベストセラーとなった。二〇一〇年に『乱反射』で第六十三回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)、『後悔と真実の色』で第二十三回山本周五郎賞を受賞。『愚行録』『乱反射』『新月譚』『私に似た人』で直木賞に四度ノミネートされている。犯罪と刑罰、宗教の功罪、格差社会などのテーマを扱い、サプライズを演出することで支持を得た著者は、社会派サスペンスの名手とされることが多い。しかし大半のミステリ作家がそうであるように、その作風は多岐にわたる。ここでは本格ミステリ作家としての側面を見ていこう。
著者は社会派かつ本格派
あえて乱暴にいえば、著者をコアな本格ミステリ作家と捉える人は少数派かもしれない。社会派のテーマを軸に据え、重い筆致で人々の営みを綴る作品群は、パズル的な謎解きの遊戯とは毛色が異なる。デビューの時期や経緯に反して新本格作家と呼ばれなかったのは、その体裁によるところが大きいはずだ。しかしそれは表層に過ぎない。著者のデビューを後押しした北村薫は、十七年後に「『乱反射』は小説の衣の下に、《本格》の鎧を見事に隠した作なのだ」「推理作家の血と汗と──心意気に眼を向け、評価しえなかったら、《推理作家協会賞》の存在意義はない」と選評に記した。これが本格のスピリットを見抜いた評であることは明らかだろう。
著者は『EQ』(一九九七年三月号)において、モーリス・ルブラン『813』の児童向け版『813の謎』に衝撃を受けた原体験を明かし、「そんな私にとって、ミステリーに最も大事なのは《驚き》です」「私の書く作品はどれも、閉ざされた空間内の事件ではないし、神の如き名探偵も登場しません」「それでも私は、ミステリーが大好きです」と述べている。三十年近く前のコメントではあるが、ここには作家性の核心が窺える。デビュー作をはじめとする諸作の仕掛けは、驚きを伴う本格ミステリと社会派ドラマを両立させる装置なのだ。