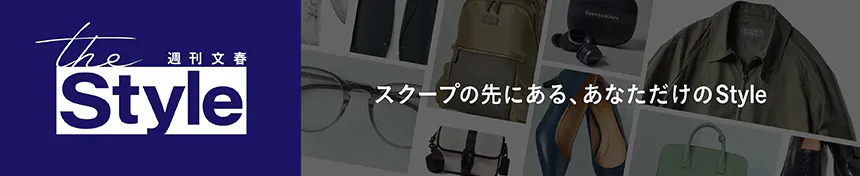今回のゲストは作家の髙村薫さん。『マークスの山』や『レディ・ジョーカー』など髙村さんが生み出してきた社会派ミステリーに魅せられてきたという岡村ちゃん。大ファンなだけに膨大な資料を読み込み、少々緊張した面持ちでインタビューに挑みました。はてさてどんな話を聞き出せるでしょうか。『週刊文春WOMAN』創刊2周年号未収録のトークも含めた完全版でお送りします。(全2回の1回め/後編を読む)
◆ ◆ ◆
1歩も2歩も引いたところで、じーっと周りを見ている子どもでした
岡村 髙村さんの幼少の頃のことを少しお伺いしたいんですが。
髙村 え、小さい頃ですか?
岡村 どんなお子さんでしたか?
髙村 集団が大嫌いで、みんなで仲良くお遊戯をするのが本っ当に大嫌い。いつも逃げてました。
岡村 人嫌いってことですか?
髙村 じゃなくて、みんなでつるんで何かをするのが大嫌いな子。
岡村 つまり、人に興味はあるけれど、群れたりはしなかった。
髙村 その通りです。基本的に、私は自分が空っぽだから、何でも受け入れられるし、「私が、私が」というのもない。何でも面白い。何でも興味がある。群れはしないけれど、1歩も2歩も引いたところで、いつもじーっと周りを見ている。そういう子どもでした。
岡村 小さい頃から読書好きだったそうですが、やっぱり小説家になるのが夢だったわけですか?
髙村 全然全然、まったく。自分が何になりたいとか、どんな大人になりたいとか、一切考えたことがなかった。本当に空っぽ。だから観察する。観察者にはなれるんです。空っぽだから。
親と反対のことをしなくちゃと思いました
岡村 ご両親の影響というのはどうでしたか? お二人とも音楽や絵画といったアートに強い関心をお持ちだったそうですが。
髙村 私は、親がいつも反面教師だったので、親と同じことは絶対にするまいと思って大きくなりました。特に母は、いろんなことを子どもに要求する人だったんです。子どもとしてはそれが鬱陶しい。
岡村 ああしろ、こうしろと?
髙村 そうそう。そして、その欲求や希望が高くて大きい。全部、私の望みではないことだったので、非常に悩まされたまま大人になりました。結果的に、親の望むことは何一つできませんでしたけど。
岡村 お母さんの要求というのはどんなものだったんですか?
髙村 まず勉強。成績です。「なんでこんなものがわからないの」と。母は化学者で非常に頭のいい人でしたから、子どもがひどい成績を取ってくると、我慢ならなかったんです。しょっちゅう怒られました。それから、小さいときからピアノを習わされましてね。ある時期からは、「ピアニストになれ」と。私にそんな気はさらさらなかった。
岡村 ストレスでした?
髙村 ストレスを感じるほど真面目にやってませんでした。親の要求に真面目に向き合うような子どもでもなかったんです、私は。