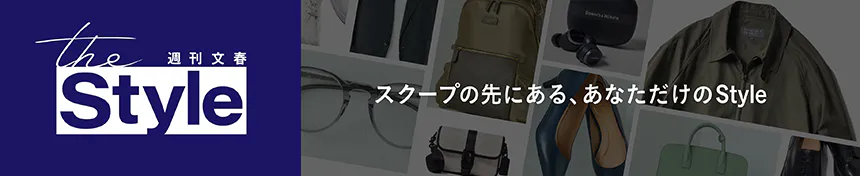ただ、踵の問題が一つのきっかけだったのか、春樹は卓球への熱を失いつつあった。前年、とにかく上達したい、選手になりたいと練習に打ち込んでいた姿からは意外ではあったが、そば屋でざるそばを食べ終わったあと、隣の席で静かにゲームをしている彼を見て、やりたいことが変わっていくのは当然の年齢であることを思い返した。
「苦労がある人、悩みがある人が、世の中をいいところにしているんじゃないかとも思うのです」
「吃音の面でも、最近春樹はだいぶ変わったように思います」
信子は言った。特にきっかけとなったのは、この日のすぐ前の2月、学校の道徳の時間に行われた、吃音についてみなで考えるという内容の授業だったという。
「学年主任の先生から、やりたいって言ってくださったんです」
4クラスそれぞれでその授業が行われると、春樹のクラスでは、10人くらいの子が積極的に手を挙げて、吃音について質問をしてくれた。みなが吃音について考えてくれているのが感じられて、春樹はその授業以降、より明るくみなと話すようになったという。
いまは、どもっても自分から話し、先生も「春樹くんってこんなに元気だったんだ」と驚くほど、様子が変わったとのことだった。
「吃音が改善しているのかははっきりとはわかりませんが、私に話すときにも、いまでは、随伴症状を伴いながらでも、積極的に話そうとしてくれるんです」
そしてそう話す信子自身もまた、変化しているようだった。
「春樹の吃音が始まってから5年が経ちました。ショックを受けて、1人孤独になって、というところから始まって、私もやっと、いまのようになれたという感じがします」
彼女は、私はいまこれを作っているんです、と言って、バッグから、紙でできた手製のものを取り出した。それは、吃音のことをもっと知ってもらうためにと、シンプルな言葉とイラストで吃音について綴った小さな冊子だった。自ら悩んできたことが、ただ息子のためだけでなく、少しでも他の人の役に立てばという彼女の思いが感じられるものだった。
「私はこれまでポジティブな面しか評価できないところがありました。勉強ができるとか、速く走れるといったことです。春樹についても、以前は他の子と比べてしまって、この子には何ができるんだろうって思ったりもしました。でも、いまは、苦労がある人、悩みがある人が、世の中をいいところにしているんじゃないかとも思うのです」
そう言った信子の柔らかな表情の奥に、この何年かの間に彼女が得てきた確固たる何かがある気がした。
【前編を読む】「自由に話せたという記憶はない」17歳で自殺未遂…言葉の詰まりを抱える男性が直面した“厳しすぎる現実”