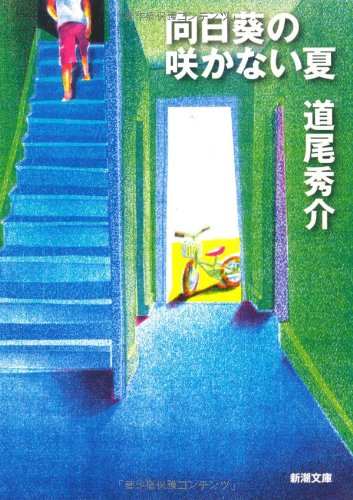驚きは目的じゃなくて手段
――それで04年に第5回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞してデビューされるわけですよね。応募先ってどのようにして決めたんですか。
道尾 まず、枚数。応募の時点では、『背の眼』はすごく長い小説だったので。それと、ちょうど綾辻行人さんや京極夏彦さんを読んでいたんですが、その綾辻行人さんが選考委員だったんですね。実際、綾辻さんがいなかったら落ちてましたから。綾辻さんが選考会でゴリ押ししてくれたんです。
――ご自身ではミステリー作家になろうとか、ホラー作品を書こうなどとは意識してなかったんですか。
道尾 自分が書くジャンルは意識してなかったですね。しないまま、けっきょく今まで来ちゃっているんですけれど。
――最初の頃はホラー作家と呼ばれることもありましたし、その後もミステリー作家だと呼ばれることが多いのでは。
道尾 やっぱりやりたいことがミステリーの範疇に入りますから。僕はなんて呼ばれてもいいし、ミステリーが好きだから、ミステリー作家と呼ばれると本当はすごく嬉しいんですけどね。でもそのジャンルというのが批判材料に使われると哀しいんです。たとえば『向日葵の咲かない夏』(05年刊/のち新潮文庫)なんて、ミステリーの歴史も現状も、ミステリーと本格ミステリーの違いもよく分かっていなかった頃に本格ミステリ大賞にノミネートされて、「あ、これが本格なのか」と思ったら、「こんなのは本格じゃない」ってバッシングされて。その時は何が起きているのか分からなかったですね。僕は何も言っていないのに、とにかく作品が可哀相でした。
その後も、なんというか、自分の飲食店を開いて、「あそこは中華料理屋だ」と言われて、他のお客さんに「こんなの本当の中華じゃない」と怒られているような違和感がずっとありました。たまにパスタを出したいなと思って出してみたら、もっと怒られたりして。ただ「飲食店」って呼んでもらえたらいいのに、と思っていました。でもそういうジャンル分けって、読者の側が自分のなかでインデックスを作るためにカテゴライズするのに必要なだけで、別に僕を分類しているわけじゃないということがなんとなく分かってきたので、今は全く気にならないです。
――最初の頃の道尾作品は終盤にそれまで見ていた景色ががらっと変わるくらいの驚きが用意されていましたよね。それが話題になっていました。以前、そういう手法をとるのは、そのほうがより読者に“致命傷”を与えられるからだとおっしゃっていましたが。
道尾 そう、そのほうが読者の懐に入り込めるという。最初から抜き身を下げて警戒されるよりも、懐に刀を隠して近づいて、懐に入り込んだところで一気に抜刀して斬るというようなやり方です。そうするとやっぱりミステリーということになるし、時に本格ミステリー呼ぶ人もいる。
――でも本当に、『向日葵の咲かない夏』は終盤に唖然としたというか。その驚きの後に立ち上ってくるのが、自分で自分の世界を築こうとした男の子の切実な思いなので、さらに打ちのめされるんですよね。
道尾 やっぱり驚きというのは目的じゃなくて手段なんですよね。読者の中に、ある感情やテーマを立ち上らせるための手段。それはいまだに続けているんですよ。ただ、その手段が必要なかったり、別の手段の方が有効だと思ったら、驚きや仕掛けというものを使わないで書きます。たとえば『向日葵の咲かない夏』と『月と蟹』(10年刊/のち文春文庫)は、同じテーマを、仕掛けを使って書いたバージョンと、使っていないバージョンです。実際、『向日葵の咲かない夏』が大好きだという人は『月と蟹』も大好きでいてくれたりするんですよね。最新刊の『スタフ』の場合は、登場人物の感情をストレートに伝えている部分もあるし、ある人物の心理描写が伏せられていて、それが最後に明らかになり、そうすることでより深く読者に感情を刻み付けるという手段も使っています。上手くミックスできるようになりました。
――そうですね、『スタフ』は集大成的なところがありますね。
道尾 ショーマンシップも身に着きましたね。『透明カメレオン』以降かな。やっぱりお金を払って読んでもらうんだから、「最終章まで読めば面白いからそれまで我慢してください」じゃ駄目なんですよね。直木賞を獲った時、北方謙三さんにも「これからは小説のための小説を書け」と言われたんです。「今までは自分のために書いていたんだろうけれど、これからはお前は小説のための小説を書け」と。それまでは自給自足的に、自分が読み返して楽しめればいいと思っていたんです。というよりも、実力的にそれしかできなかった。その面はその面で残して、プラスαでもっと難しいことをやろう、ということで、ショーマンシップを発揮できるようになったんですよね。人間って損得勘定が働くのか、前半中盤がつまらないほうが最後のサプライズのインパクトを大きく感じるときがありますけど、ページをめくるのが楽しくて、でも最後のインパクトは変わらない、というものが書けるようになりました。