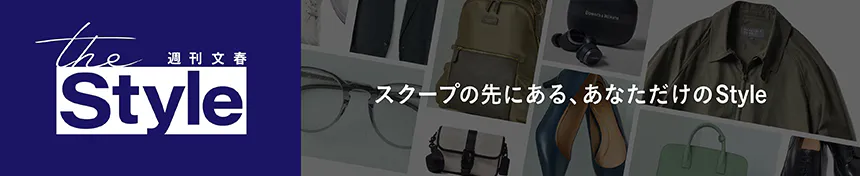都会の高架下を歩くと、コンクリート壁に吹き付けられたスプレー文字――グラフィティをいくつも見ることができる。通行人のほとんどは風景として気にもかけないか、不法な落書きに眉をひそめるだけで通り過ぎていくだろう。それが人の目を盗んで書き残されたイリーガルなメッセージであると捉える人はほとんどいない。
“グラフィティは〈描く〉のではなく〈書く〉のだという。グラフィティは全て「俺はここにいたぞ」という署名で、それを記した者のこともアーティストではなくグラフィティライターと呼ぶ。”(本文より)
『イッツ・ダ・ボム』は、謎に包まれたグラフィティライターを取り巻く小説だ。稀少なトレーディングカードのカラーコピーを路上に放置する、という活動が著名写真家の目に留まったことから注目を集めた彼は、カード名を借りた「ブラックロータス」として次々に作品を発表する。素性が明らかになっていないことと風刺的なユーモアから、日本のバンクシーと称され、世間に名を知らしめる。
だが、真の謎は人物でなく動機にある。これは「誰」ではなく「なぜ」を追うミステリーなのだ。彼がグラフィティによって挑発しようとしているものは何なのか。物語を追ううち、単なる壁の落書きは人間の叫びに変貌していく。
グラフィティは複雑な境遇に立つ文化だ。ライターは、スプレーやシールで街場に自らの名を刻む(仲間内で「ボム」と呼ばれる)。自己顕示欲を器物破損行為で満たしているだけだと冷ややかな視線を向けられる一方で、キャッチーなスタイルはファッションアイコンとして商業的に利用されてもいる。渋谷に行くと、落書きを禁じる張り紙とプロの手によるグラフィティ風壁画の両方が目に入る。違法性を内包しているため、アートとしての公認は得づらいが、逆にいえばそれがグラフィティ独自の特色であり、反体制的な自己表現のアイデンティティだ。共感と反発。排除と利用。先鋭と迎合。相反する要素がせめぎ合って同居しているのがグラフィティ文化なのである。
内実がどうであれ、文化と呼ばれた時点からあらゆるものは価値化を免れない。ごく個人的な衝動の発露であったはずのものも、より大きな構造の一部に組み込まれている。それは現代で「反抗」をすることの困難さそのものである。
逸脱者としての不良すら文化のラベルを貼られ社会的役割を担わされる時代に、どのような形で抗いの声を発信できるのか? この問いに、ブラックロータスは驚くほど具体的な形でひとつの答えを提示している。アウトローを中心に据えつつ単なる犯罪賛美にはとどまらず、あくまでメッセージであることにこだわり続ける、街の風景が変わる可能性を秘めた一冊だ。
いのうえさきと/1994年愛知県生まれ。川崎市在住。成城大学文芸学部文化史学科卒業。2024年『イッツ・ダ・ボム』(「オン・ザ・ストリートとイッツ・ダ・ボム」より改題)で第31回松本清張賞を受賞しデビュー。
しなだゆう/作家。ダ・ヴィンチ・恐山名義でライターとしても活動。最新刊『納税、のち、ヘラクレスメス のべつ考える日々』。