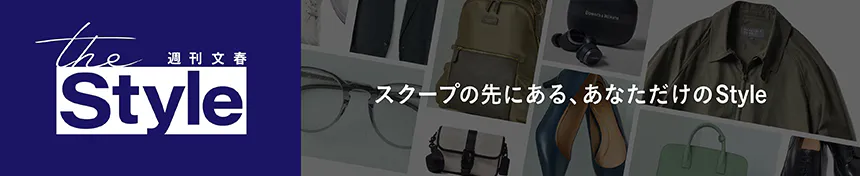母は自ら、娘の息の根を止めた
母は2歳の妹の首に日本刀を当て、息の根を止めた。大島は母と一緒に在郷軍人に銃剣でとどめを刺してもらう直前、はぐれていた父と兄に見つけられ、救われた。生存者はわずか百数十人だった。
敗戦まで大島一家は、現場から北へ約30キロの興安(現・ウランホト)の街で工務店を営んでいた。街が空襲された11日朝、自宅へ水筒の水をくみに来た下士官は、「軍隊と一緒にいれば大丈夫です。大島さんたちだけなら、なんとかなるかも……」と言った。その意味に気がついたのは戦後になってからだったという。
軍関係者やその家族は、11日に列車で脱出していた。
大島は戦後、事件の関係者から証言を集め続けた。その中に、興安の特務機関に庶務係として勤めていた女性がいた。
その女性によれば、父親が10日に銀行へ預金をおろしに行ったが、軍が全部差し押さえ、民間人は引き出せなくなっていた。11日に出勤すると、職場は移動の準備でごった返していた。経理課で、札束が包みからはみ出しているのが見えたという。
特務機関の職員だった自分だけが列車に乗れたため、家族6人と生き別れてしまった。帰国して約10年後、家族全員が葛根廟で命を絶たれたと知った。「悔やんでも悔やみきれない思いで生きてきた」と、女性は語っていた。
大島は「自分たちを置き去りにした軍隊に、憎しみや悔しさはさほど感じない」と言う。「ただ痛感したのは、軍隊が守ろうとしたのは、国体とそれに連なる軍隊の組織だけだったということ」。
現場に取り残された乳幼児も多く、少なくとも32人が残留孤児になった。「地元の人たちが育てたのです。敵を『鬼畜米英』と呼んでいた自分たちに、同じことができたでしょうか?」
その他の写真はこちらよりぜひご覧ください。