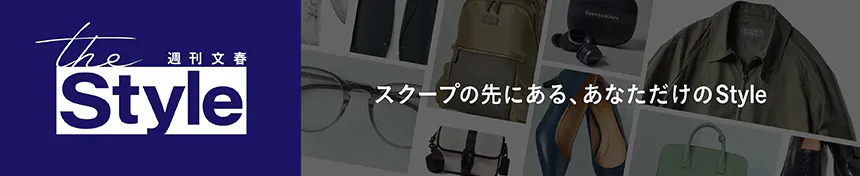「別に“子連れ”が私のポリシーではないのね」
そのなかでアグネス自身が批判に真正面から反論したのは、せいぜい「アグネス・バッシングなんかに負けない」と題する月刊誌への寄稿(『中央公論』1987年10月号)ぐらいであった。その内容も、子供を連れての出勤に理解を求めることよりもむしろ、批判記事から広がった不正確な情報を正すことや自分が標的になった原因の分析に重点が置かれていた。
そもそもアグネスのなかでは、子連れ出勤を通じて社会に何かを訴えようなどという意図はなかった。あるインタビューでは、《別に“子連れ”が私のポリシーではないのね。むしろ自分が子供といられる、母親として最大の努力をしたいと思って、それがあの形になったと思うんです。私が芸能人じゃなかったら1年半仕事を休むことを考えたかも知れないし、あるいは一番近いところに預けたりとか。(中略)でも芸能人という私の立場から見たら(子連れは)可能なんですよね》と、こうした選択をしたのはたまたま自分が芸能人だったからだと認めている(『週刊明星』1988年10月27日号)。
アグネスに対して向けられた批判の声
アグネス批判も当初は、そうした彼女個人の言動に向けられることが多かった。批判派の一人は、地域の保育所の完備など社会的な子育て支援を求めるのは当然だと認めながらも、働く人間として仕事のあいまに母乳を与えてまた戻ってくるということは、あまりに甘ったれた夢物語だと切り捨てた。
週刊誌に寄せられた一般読者からの意見(『週刊文春』1988年10月20日号)のなかにも、たとえば、20代後半の女性会社員は「どこの会社でも、結婚して子供を産んでからも働けるのはよほど会社側にメリットのある人間であり、育児施設の設置など問題外。アグネスは、自分がそういうメリットのある特別な人間だということがわかっていない」という趣旨の主張をしている。
あるいは幼い子を抱えながら働く女性からは、勤務先ではなかなか休ませてもらえず、子供が病気のときも家に一人置いたまま、心苦しくも出勤せねばならなかったという体験から「社会に出た限りは何かを犠牲にしないといけない。アグネスのように子供は四六時中自分の手元に置いておきたい、仕事も捨てたくないのは欲張りすぎだ」との声が上がった。
しかし、いずれの意見もアグネスを批判しながらも、当時の日本社会で女性たちが出産後も働き続けるにはさまざまな支障がともなったという現実を浮き彫りにしていたことは一目瞭然である。