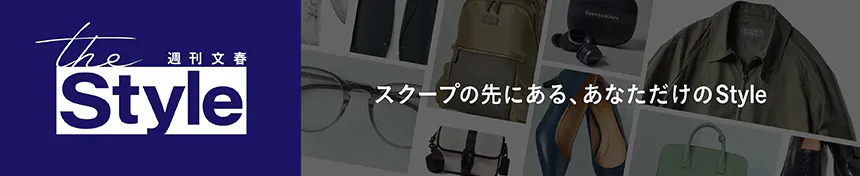今から80年前、太平洋戦争末期の1944年10月に始まった「特攻」は、終戦の日までおよそ10か月にわたって続けられ、隊員たちは次々と出撃を命じられた。その最中、彼らに続けとばかりに「一億特攻」を叫ぶ声が、日本中で広がっていった。
しかし戦後、特攻の戦果は誇張と虚偽に満ちたものであったことが明らかになり、国民の価値観は一変。多くの人々は自らも「一億特攻」に加担していたという事実を忘れていったが、そんななかでも自らの責任と向き合いながら生きた人物がいた。
『一億特攻への道 特攻隊員4000人 生と死の記録』(文藝春秋)から一部を抜粋し、紹介する。(全2回の2回目/はじめから読む)
◆◆◆
少しずつ知ることとなった「特攻の真実」
日本が突き進んだ「一億特攻への道」は、昭和20年8月15日の正午、ポツダム宣言の受諾をラジオから国民に伝えた玉音放送を境に、突如終焉を迎えた。海軍では、沖縄特攻作戦の指揮を執った司令長官のひとり宇垣纒中将が、15日午後、22名の搭乗員を引き連れて沖縄周辺のアメリカ艦隊目がけて出撃し、陸軍では満州方面で、進撃をやめないソ連軍に向けて出撃した特攻機が知られるが、いずれも軍の正式な作戦ではない。
やがて国民は、戦時中の軍やメディアがひた隠しにしてきた「特攻の真実」を少しずつ知ることになる。特攻が大々的な戦果を挙げていると報じていた大本営発表は、嘘にまみれた虚飾だった。特攻の始まりは、隊員たちの自発的な愛国心の発露ではなく、失態に失態を重ねて戦況を悪化させた軍首脳による事実上の強制だった。にっこり笑って出撃していったはずの隊員たちの多くは、最後まで葛藤を抱いて死んでいった。「君たちだけを死なせない、私も必ず後から続く」と送り出した司令官のほとんどは、約束を守らなかった。
フィリピンで陸軍の特攻作戦の指揮を執った第四航空軍司令官の富永恭司中将は、東京からの命令を待たずに勝手に台湾に逃げ帰り、多くの隊員や航空隊要員を置き去りにし、戦後、特に糾弾されたひとりだった。その一方で国民のほとんどは、みずからも「一億特攻」に加担したという事実を忘れていった。
だが、己の責任に向き合いながら戦後を生きた人もいた。そのひとりが、戦時中、福岡県八女郡の黒木国民学校の校長を務めていた平島大勝(ひらしま・だいしょう)さんだった。平島さんは、八女郡最初の特攻戦死者である河島鉄蔵さんの遺族に地域の教師たちが送った「大君の楯」に言葉を寄せたひとりだった。