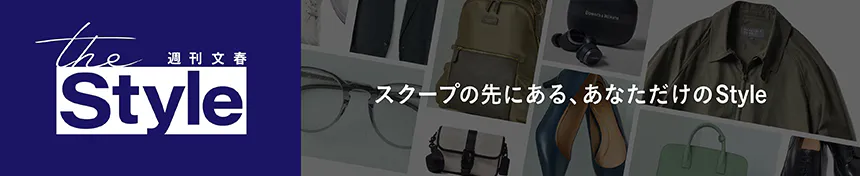――運命の出会いですね。いくつのときですか、それは?
坂本 中1だとすると13歳ぐらいですね。春翠先生の語りは七五調というか、わりとそういうタイプの方だったんですよね。(『夢みるように眠りたい』での春翠先生の語りを真似て)「紫紺の空には星の乱れ。緑の地には花吹雪。千村万落、春長けて。春や春、春、南方のローマンス」とか、「おお、夢か幻か、黒頭巾は桔梗姫のあとを追って、悪漢一味を追跡した」みたいな。そういうのが面白いわけですよ。それで真似してるうちに自分でもやってみたくなってくるわけですな。
それまで講談とか浪曲も漠然と知ってたし、落語は好きでちょろちょろ聞いてましたけど、活弁は知りませんでしたからね。でも、面白いなと。しかも映画と演芸のちょうど中間というかね、両方の特質を持ってるなと思った。そう思っていた矢先にですね、うちの中学校の2年生の課外授業で、きょうは活弁を観に行くと言われて。こんなことってあるのかしら? と思いました。
活弁という芸に惹かれていく
――そのタイミングで。まるで活弁に引き寄せられるかのような展開ですね。
坂本 王子の北とぴあかな。チャップリンの『キッド』(1921年)を弁士と楽団の生演奏でライブ上映するので、生徒全員で観に行ったんですよ。そこで初めて生の活弁に触れたわけですね。そのときの弁士は澤登翠さん。片岡一郎さんの師匠で、春翠先生のお弟子さんですよ。それで私は初めて生で観て。何というこのライブ感の面白さ。あたかもトーキー映画を見るようなね。
『キッド』はサイレントなんだけれども、普通の映画に感じるわけです。ときどき、「あ、そうだ、横にいるあの女性がしゃべってるんだ」と気づくわけですけど。だから映像も語りも音楽も独立してるはずなんですけど、それが合体してるというのが、ほかの芸とはまた違うと感じてね。しかもしゃべる人間が真ん中にいない。あくまでも映画が主体なんですね。そこにカルチャーショックを受けました。
「弁士っていう仕事がちょうど自分の感性にフィットしたんです」
――なるほど。
坂本 たとえば私は、水木先生のマンガでも鬼太郎よりねずみ男が好きだったりするわけですよ。だから脇役が好きなんだね、メインより。つまり、映画がメインだとすると、脇が弁士なんですよ。
だから、弁士っていう仕事の立ち位置がちょうど自分の感性にフィットしたんですね。それでやってみたくなってね。水木先生への情熱がそれまで41度ぐらいあったけど、活弁を知ってから37度8分ぐらいになっちゃって。
高校に進んで、さらに映画の熱が強くなりました。しかも学校が池袋にあったんですよ。まだ改築前の文芸坐(現・新文芸坐。古い映画を見せる名画座)があった頃の。それで学校にはあんまり行かず、文芸坐で映画ばかり観てたんですよ。それでやっぱり活動弁士がいいやと思って、高校をもうやめようと。水も合わないしね。みんなと話題が全然違いますから。