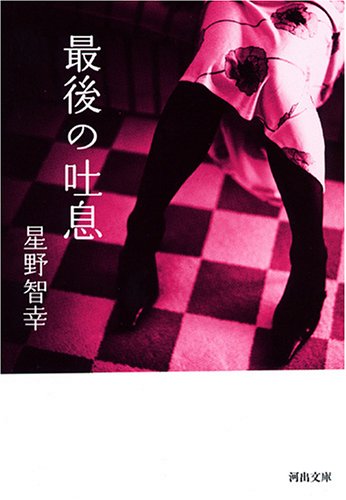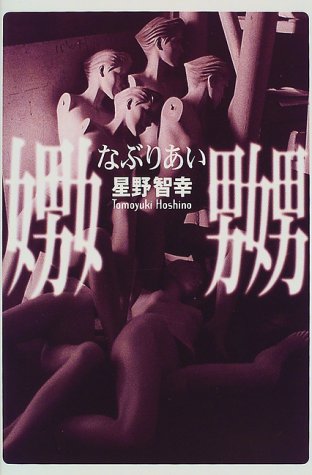デビュー当時に考えていた「先鋭化」というキーワード
――「心の闇」という言葉も流行り出しました。
星野 そうそう。「心の闇」という言葉が出てきたのもあの頃でした。そういう言い方で全部まとめられてしまうので、その人たちの本当の悩みや実像というのはわからないまま、単純化される。そういう状況に対して、レッテルで決めつけられるのではないあり方を、人の生き方にせよ、社会のあり方にせよ、ありうることを小説で見せたいというのがあったんです。
――新人賞に応募するために書き始めたのは、どんな作品だったのですか。
星野 いろいろというか、バラバラというか。自意識過剰であることを意識し続ける小説のような、読んでいて耐えがたいものとか(笑)。相撲小説も書きました。
――相撲ですか?
星野 今考えると、これは安部公房の「時の崖」という、ボクサーの意識の流れを書いた小説の影響だと思いますけれど。3分くらいの取り組みが永遠のように引き延ばされていくような(笑)。そういう、若者がやりそうなことをいっぱいやっていましたね。その後、ラテンアメリカの小説と、自分のラテンアメリカの体験と、そのあと日本で生きている自分を盛り込んで書けたのがデビュー作でした。
――文藝賞受賞作の『最後の吐息』(98年刊/のち河出文庫)ですね。中南米の濃密な空気や植物の香りが漂ってくるような作品でした。
星野 書いた時に「あ、今まで応募してきた習作と手応えが違うものを書いたな」という実感があったんですよね。だから、これでどこにも引っかからなかったら、自分の文学は業界からは認められないのだから、もう諦めようと思いました。
――そのラテンな感じの作風でいくのかと思ったら、2作目は『嫐嬲』(99年河出書房新社刊)ですよね。表題作は現代日本の男女3人の話ですが、じつはそこにジェンダーの問題が絡んでいる。
星野 どういう動機だったのか詳しくは憶えていないけれど、ひとつはラテンアメリカじゃなくて完全に日本を舞台にした日本の人たちの話も書いてみたいと思ったんですよね。なにしろ「最後の吐息」が読みにくいと言われましたから(笑)、もうちょっと読みやすい一般的な小説の形態を書いてみようと思って。今読むと全然読みやすくなっていないんですけれど、でも、あの時はそういうことをかなり意識して書いたんです。テーマとしては、ジェンダーの境界を越えていくというか、境界を無効にしていくことがテーマにはなっていて、それと同時にテロの話も入っていますよね。
――はい、彼ら3人が最初はテロと称して小さないたずらを起こしますが、それがだんだんと……。
星野 ああ、思い出した、あの頃キーワードとして考えていたのは「先鋭化」でした。自分の生きている社会を変えるために正義を行おうとした時、それが先鋭化していくとたちまち冷酷で不寛容な暴力になっていく。何かを社会的な観点から変えていくために一番避けなくてはいけないのは先鋭化なんじゃないか、というようなことを考えていました。
デビュー作の「最後の吐息」はメキシコが舞台ですけれど、結構政治的な題材を思いきり扱っているわけですよね。それを日本に持ち込もうとしてみたのが「嫐嬲」でした。「最後の吐息」でもテロが起きますが、それが日本だったらどうなっていくのかというのが「嫐嬲」だったような気がします。