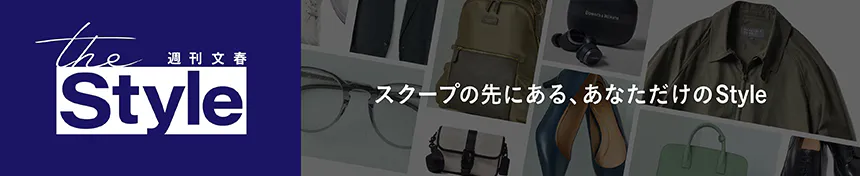地主の横暴に抗する農民組合を援助して起った広汎な文化人の闘争に参加し、堂々官憲と闘った筆者の描くその顛末!
初出:文藝春秋臨時増刊『昭和の35大事件』(1955年刊)、原題「木崎村暴動事件」(解説を読む)
敗戦後の青年層に広がった社会革命運動への熱
敗戦直後の日本に思想的な颱風がやってきて、あらゆる面で価値転換が行われたことはだれもが体験したことであるが、第一次大戦後、即ち大正末期から昭和の初めにかけても同じような現象があらわれた。特にその影響を強くうけたのが青年層であったことも、変りがない。
当時のスローガンであった“改造”や“解放”などというのは今も残っているが、そのほかに“ナロード”というロシア語が日本の青年たちの間に流行した。これは“民衆”という意味で、“ヴ・ナロード”(民衆の中へ)というのが、そのころの合いことばとなり、若いインテリゲンチャの血を沸き立たせたものだ。これは初めは主としてロシヤ文学、特にツルゲネーフの小説などからきたもので、さらにソ連におけるプロレタリア革命の成功が強い刺戟となった。この思想にゆさぶられて“民衆の中へ”とびこんで行ったものを、“ナロードニキ”といった。
東大の「新人会」、早大の「建設者同盟」などの学生団体は、こうした時代的背景のもとに生れたのであって、今日社会党の幹部になっている人々は、ほとんどこの時代の第一期生と見てよい。特に「建設者同盟」に属していた人たちは、農民運動の“処女地”(これもツルゲネーフの小説の題名だ)を開拓するために、各自手分けして地方農村へ入って行った。三宅正一、稲村隆一は新潟へ、川俣清音は秋田へ、平野力三は山梨へ、浅沼稲次郎は関東へという風にだ。そこでかれらは農民組合をつくり、後にはこれを地盤にして代議士に出たのである。中には平野のように、保全経済会に関係して落伍したものもいるが、多くは今もその地盤を守りつづけている。
娘を売ったお金で生活…… 貧しさを極めた農村の怒りが爆発
この時代のもっとも大きな出来事の一つとして、当時連日新聞紙面を賑わし、社会に大きなショックを与えたのが、新潟県木崎村の無産農民小学校事件である。これは同地における小作争議と共に発生したものであるが、全日本的な話題となり、中央の文壇、思想界の進歩的分子がこぞって、いや、“ブルジョア派”のレッテルをはられていたものまでが、これを応援し、その後にできた言葉でいうならば、一種の“人民戦線運動”にまで発展したのである。
新潟県は、日本一の米作地帯であると共に大地主の多いことで知られている。米だけの単作で、それ以外に収入の道がないので、あまった人口は大都会に出て、男は三助となり女は娼妓や女工となった。そのころの農会の統計によると、新潟県の小作人は、1人1日22銭5厘の生活をして、しかも年に一戸あて450円以上の赤字が出ることになっていた。この生ける屍のような生活さえつづけて行くことができなくて、娘を売った金で小作料を支払わねばならなかったのである。
そこへ社会革命の情熱に燃えるインテリが入って行って、大地主に対抗して生活を少しでもよくするには、団結によるほかはないことを説いたので、農民組合が燎原の火のようにひろがって行った。そしてついに劃期的な小作争議となって爆発したのは、大正が昭和に移った年の5月である。