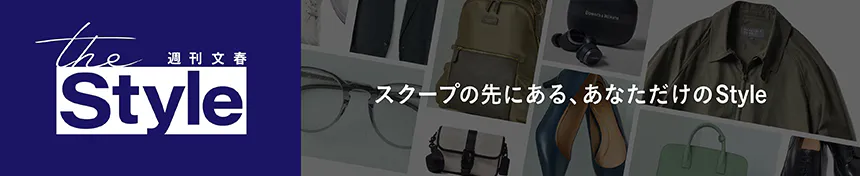ドイツ人捕虜に対する視線にも、そのあこがれとコンプレックスがぬぐいきれずに出ている。
新聞その他、事件について書かれたものは、日本側の捕虜の扱いが人道的であり、妻を追って自殺した夫の行為を称賛して夫婦の美談とするものが圧倒的に多いが、そこにはどこか居ずまいの悪さが感じられる。事件を通して、国と国民がまだ成熟していないことを悟らされたようにも思える。しかし、国も国民もそのまま背伸びを続け、昭和に突入する。
一審、二審とも死刑判決…「顔色変じて土のごとくなり、両眼は血走りぼうぜん」
田中徳一は一審、二審とも死刑判決を受け、二審判決の際は「顔色変じて土のごとくなり、両眼は血走りぼうぜん」(1917年7月5日付九州日報)。そして、事件から1年余り後の1918年3月10日、長崎監獄片淵分監で処刑された。12日付福岡日日によれば、娼妓をしている妹に1通の書き置きを残したという。自分が犯した罪の報いとはいえ、彼の人生も恵まれていたとはいえない。
イルマ殺しで、ドイツ政府は当時中立国だったアメリカを通して日本側に強く抗議した。しかし、ザクサー大佐の報告書に「日本の軍事・民事関係の役所は、これまで全てについて非常に寛大な対応で自由にさせてくれました」とあるように、日本側の事件対応はおおむね良好で、それ以上の国際問題には発展しなかった。
名簿に残された「埋葬地不明」
1917年9月24日付東朝には、社会面ベタで横浜港にオランダ船「オレンジ号」が寄港した記事が載った。まだ欧州で戦争は続いており、オーストリアの中国公使らドイツ、オーストリアの官吏をアメリカ・サンフランシスコに送るための船だったが、記事の最後にこうある。
「横浜よりの乗客としては、先に福岡で凶刃に倒れたイルマの遺児フォルスト・エルデルヒ・フォン・ザルデルンが帰国するため、保母アンナに伴われて乗船した」
報道解禁直後の「婦人公論」1917年5月号で、「情痴文学」の作家として知られた近松秋江は江戸時代の近松門左衛門の「心中もの」やフランスの作家モーパッサンの短編を引き合いに、事件について述べている。
「ザルデルンの妻は人手に斃(たお)れて死んだのであるが、夫が悲歎(嘆)の餘(余)りその後を追ふ(う)て自殺するに到つ(っ)て、それは情死の形式になります」
ザルデルン大尉は遺書で2人の遺骨をドイツの土地に埋葬するよう求めていたが、「独軍俘虜概要」の名簿で大尉の項の末尾には「埋葬地不明」とある。大尉とイルマはどこに眠っているのだろうか。
【参考文献】
▽久留米市文化財調査報告第306集「久留米俘虜収容所Ⅴ ドイツ兵捕虜と家族」久留米市教育委員会 2011年
▽「福岡県警察史 明治大正編」 福岡県警警察本部 1978年
▽黒田静男「地方記者の回顧(大正時代 月曜附録から学芸欄の創設)」 黒田静男記念文集刊行会 1963年
▽ 奈良岡聰智「第一次世界大戦と対華二十一カ条要求」=筒井清忠編「大正史講義」(ちくま新書、2021年)所収
▽水野廣徳「大正戦役史」=「明治大正国勢史第2巻」(実業之世界社、1929年)所収
▽内海愛子「日本軍の捕虜政策」 青木書店 2005年
▽板谷敏彦「日本人のための第一次世界大戦史」 角川ソフィア文庫 2020年
▽鬼頭鎮雄「はかた大正ろまん」 西日本新聞社 1981年
▽読売新聞西部本社編「福岡百年」 浪速新聞社 1967年
▽江頭光「ふてえがってえ福岡意外史」 西日本新聞社 1980年