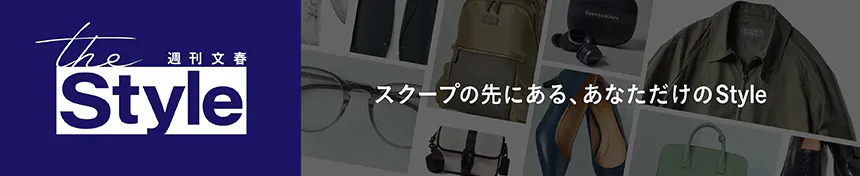都内23区内の火葬事業の7割超を握る会社、東京博善。親会社の廣済堂が中国人実業家・羅怡文氏グループの傘下企業となり、火葬料金の値上げが行われた。
それに対し葬儀業界は「火葬は公共性の高いインフラなのに許せない!」と反発し、マスメディアでも連日、火葬料金の値上げに関する報道が流れた。いったいなぜ、東京博善は業界の反発を受けながらも火葬料金の値上げに踏み切ったのか。
ここでは、日本の火葬と弔いの歴史に迫ったジャーナリスト・伊藤博敏氏の著書『火葬秘史: 骨になるまで』(小学館)より一部を抜粋し、火葬料金値上げの背景を紹介する。(全3回の3回目/1回目から読む)
◆◆◆
「火葬場は社会インフラの一部なんです」葬儀業界に衝撃を与えた東京博善
東京博善を巡る環境は大きく変わり、時代の流れに沿うものとはいえ「普通の会社化」は、葬儀業界に衝撃を与え不満が渦巻いた。東京博善との交渉窓口でもある濱名雅一・東京都葬祭業協同組合理事長の次の言葉は、業界意見を代表するものといえよう。
「火葬場は社会インフラの一部なんです。本来であれば公共事業として地方公共団体がもっと安価か、もしくは無料でやるもの。営利企業が社会インフラの利用料を自身の都合で変えることがあってはならないでしょう」
火葬が「公共インフラ」だという主張は誰もが等しく口にし、それは事実である。もともと火葬料金は、1927年以降、警視庁の管理下に置かれ許可制だった。戦前の統制経済を思えば当然だが、終戦後の1946年に管理は東京都経済局に移り、物価課が統制物資価格としていた。戦後インフレに対応する措置だったが、1954年に統制最後の品目だった火葬料の「認可制の廃止」が通告された。
以降、自由な価格設定が許されてきたが、僧侶経営を引きずる浅岡眞知子元社長の時代までは、葬儀業界との調和が優先され勝手に値上げすることはなかった。