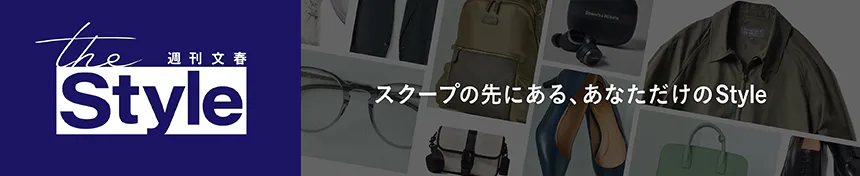PCRには、増やしたいDNAの最初の20ほどの塩基配列と相補的な関係になるように配列を人工的に合成した短いDNAを用います。これを「プライマー」と呼びます。プライマーは、増やしたいDNAの起点となる部分と結合し、プライマーと結合したDNAは連鎖反応を起こして増幅していきます。
実際にはきっちりとした温度管理などが必要ですが、ここでは原理だけを説明します。
まず、容器に増やしたい特定のDNAと、そのDNAの起点となる部分と結合するように設計した2種類(DNAの鎖が2本あるので)の人工プライマー、高温でも働きを失わないDNAポリメラーゼ(合成酵素)を投入します。次に容器内の温度を95度に上げて、増やしたい特定のDNAの2本の鎖をほどきます。
DNAの鎖は水素結合でつながっていますが、水素結合は温度が上昇するとほどけてしまい、摂氏95度になるとほぼ離れてしまうのです。DNAはほどけると2本の1本鎖のDNAとなります。DNAがほどけたら容器内の温度を60度前後まで下げます。温度は塩基配列の長さや、含まれる塩基の種類に合わせて調整します。
温度が下がると、1本鎖のDNAのそれぞれにプライマーが結合し、次にまた少し温度を上げるとそこを起点にしてDNAポリメラーゼが1本鎖のDNAに相補的な塩基を持つ核酸をつなげてDNAを合成していきます。
合成が完了すると2本鎖のDNAができあがり、元のDNAは倍になります。この反応を繰り返すことで、目的とするDNAは指数関数的に増えていきます。これがPCR反応の仕組みです。
PCR法が初めて論文で発表されたのは1985年12月のことで、その功績により1993年にはノーベル化学賞が授与されています。論文発表からさかのぼること2カ月、1985年10月にアメリカのソルトレイクシティーで開催された米国人類遺伝学会で、PCR法が、彼の部下のランドル・サイキ氏によって初めて発表されました。
余談ですが、ソルトレイクシティーにあるユタ大学のハワード・ヒューズ医学研究所の博士研究員(ポスドク)としてがん遺伝子の研究をしていた私は、偶然にも、会場の照明係を務めていて、発表の現場に居合わせることができました。
簡単に遺伝子を増やすことができる、びっくりするような単純な方法に愕然としたことを憶えています。
新型コロナウイルス感染症の診断にPCR検査が重要な役割を果たしているように、PCR法はいまやさまざまな分野で幅広く応用されています。分子生物学や遺伝子の分野は言うに及ばず、犯罪捜査や親子鑑定にも利用されています。
私と科学警察研究所の研究員が共同で開発したDNA鑑定システムは、私が発見したVNTRマーカーをPCR法で効率的に視覚化するシステムです。これにより、それまでは1週間から数カ月かかっていた解析が2時間程度でできるようになりました。
PCR検査を“すり抜けた”変異ウイルス
PCR検査機器は、遺伝子(DNA、RNA)やその一部分をターゲットに設定し、それに相当するDNAを増やす機器です。RNAの場合には、まずRNAをDNAに変換するステップが必要です。
新型コロナウイルスのPCR検査では、被験者の唾液などの検体を機器に投入し新型コロナウイルスに特有の遺伝子が検出されれば陽性と判定され、検出されなければ陰性だということです。
ゲノム解析により新型コロナウイルスの遺伝子の全塩基配列は明らかにされています。そのため、PCR法で新型コロナウイルスの遺伝子だけを増幅することはそれほど難しくはありません。