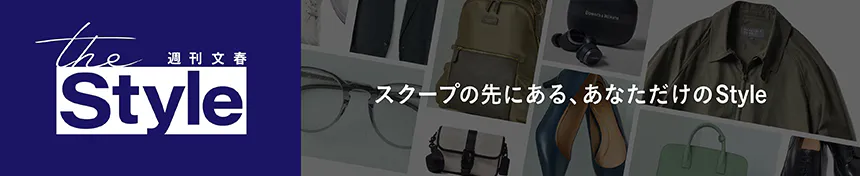一事が万事、そんな調子で、命じられたことを完璧にこなし、少しずつ認めてもらい、やがて先輩たちの仕事のサポートに回るように。板場での「型付け」を、大柄のものからさせてもらえるようになったのは、1年後。コマ(糊を伸ばす板の道具)の持ち方、型紙の扱い方などについても「ひたすら先輩を真似ました」と振り返る。
「気づいたら、あっという間に10年経ち、20年経っちゃったという感じ」だと言い、その傍ら、「染色への興味から入り、着物全般の知識が乏しかったので文献で勉強しました」。
ワイドな視野でのヒント
——ということは、先輩職人と本が“師匠”でしたか?
「はい。あと、大局で社長。オーダーをくださったお客さんや呉服屋さんの意に沿うように仕上げるのが私たちの仕事だと学ばせてもらいました。着物は染めて終わりじゃなくて、お客さんが着て完成だということ。それに……」
——それに?
「すごく助かることがよくあります。先日も、型紙の選定を悩んでいたとき、旅の雑誌を見せてくださり、その中の写真から大きなヒントをもらったんです」
一つひとつの工程から、その先を見る。着物や柄を俯瞰して捉える。木も見て森も見る、といった富田さんだからこそのワイドな視野だ、と思った。
話を聞いた後、西條さんが板場で「型付け」の作業を見せてくれた。
まず、色糊づくり。もち米と塩と糠(ぬか)を混ぜて蒸した「元糊」に数種の染料を加え、お湯で溶きのばしてつくる。そして、12万種類もあるという伊勢型紙から、このときはとても細かな波の柄のものを選んだ。
作業台の一枚板はモミの木で、6.5メートルきっかり。「剣先」と呼ぶ片端の厚みが、徐々に薄くなっている。反物は13メートル。剣先で折り返し、板の表裏に白生地をぴったりと張り付ける。その生地の上に型紙を置き、コマで糊を置いて生地に白く染め抜くための文様をつけていく。
型紙の縦幅は約30センチ。「星」と呼ぶ点を目印に、1ミリたりとも狂わず、つなぎ目をピタリと合わせ、数十回の型送りが繰り返された。ちょっとやそっとでない集中力。横で見ていて、息をのむばかりだ。そして糊が乾くと「地染め」という、塗りつける工程。その次に、生地を「蒸箱」に入れる、摂氏90~100度で20分ほど蒸す。蒸し上がったら生地を水洗いし、糊や余分な染料を落とす。型付けの際に糊を置いた部分が模様として浮き上がってくるそう。
「経験と勘ですね」
が、すべてが終わってからの西條さんの一言。かっこよすぎる、と思いきや、「職人の理想は死ぬまで仕事をすることだね。工房で倒れて亡くなった人が一人いましたよ」と富田さんがとどめを刺した。
撮影◎川本聖哉