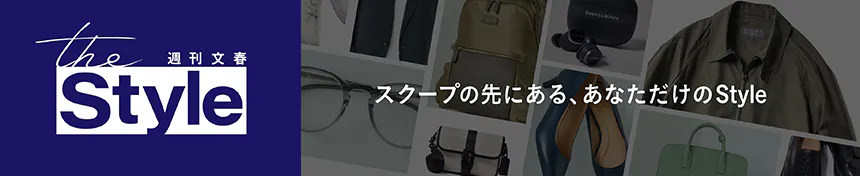埼玉県八潮市の道路陥没事故は氷山の一角にすぎない——。八潮の事故を受けて設置された有識者会議委員長で、土木学会元会長の家田仁が警鐘を鳴らす。
◆◆◆
日本に潜在するインフラのリスク
1月に発生した埼玉県八潮市での道路陥没事故では、トラック運転手の男性が巻き添えになりました。この事故の原因がなんであったかは、いずれ専門家による究明がなされることでしょう。原因が何であれ、この事故はインフラ全般の潜在的なリスクを物語るものです。全国どこでもインフラに関わる事故のリスクを抱えていると考えるべきです。いたずらに危機感を煽りたいわけではありませんが、国民の皆さんには、あの事故を契機にインフラ整備についての認識を変えていただきたいと思っています。そのためにはまず、インフラが我が国でこれまでどのように整備されてきたか理解しなければなりません。
いま使われている、日本のインフラ、すなわち、道路や橋、上下水道などのほとんどは、戦後の高度成長期からバブル崩壊までに作られたものです。当時の時代精神はスクラップ&ビルド。とにかく早く作ることが最優先され、いずれ古くなったり壊れたりしたら、更新すればいい、と考えられていました。用地取得にかける時間を節約するために東京の水路の上をうねるように建設された首都高速道路が、その典型例です。高度成長期はとにかく日本全国津々浦々にインフラを張り巡らせる“水平展開”の時代でした。同種のインフラを全国へと普及させていく“水平展開”がどんどん進むと同時に、これまでの整備理念や技術とは質的に異なるハイグレードなインフラ整備も進められるようになりました。ETC導入や歩行者・自転車のための道路充実や都市の景観改善、あるいは河川や湖沼などの環境整備などはその典型で、私はこれを“垂直展開”と呼んでいます。しかし、高度成長期以来、率直に言ってやはり“水平展開”に極めて大きなウェイトが置かれ、“垂直展開”はまだまだ不足しています。