コロナ禍で、明確なエビデンスもなしに「自粛要請」が繰り返される日本。「緊急事態宣言」も、本来あるべき「議論」を経ずに、何となく「空気」を読むように発出され続けている。こうした「議論ができない日本人」を問題視する歴史学者の與那覇潤氏と文芸批評家の浜崎洋介氏の対談を掲載する(この対談は、ジュンク堂書店池袋本店での「與那覇潤書店」の開催を機に、2021年6月11日、「店主」の與那覇氏が浜崎氏を招く形で行なわれた)。
緊急事態宣言に「飽きた」日本人
與那覇 新型コロナウイルスへの対応をめぐって「国論分裂」といってよい状況にあるいま、本日(2021年6月11日)は浜崎洋介さんと「日本人はなぜ議論ができないのか?」「いつからできなくなったのか?」について、じっくり考えたいと思っています。浜崎さんは文芸批評家という「ことば」のプロであると同時に、特に戦後文学に強い「歴史家」でもあるということで、お招きした次第です。

與那覇潤氏
意見が異なる人とも、どこで意見が食い違っているのかを見極めながら一歩一歩、対話していく。そうした姿勢が「意見が分かれてしまう問題」に対しては求められるはずなのに、日本人はこういう「議論」が非常に下手ですね。
浜崎 「議論が下手である」以前に、そもそも「議論をしない」という感じすらしますね。
與那覇 コロナで興味深かったのは、これまでの3回(対談時点)の「緊急事態宣言」に対する人々の反応が、それぞれに違っていたことです。
1回目の時(2020年4月~5月)は――浜崎さんも僕もこの時点から「過剰対応」だと判断していましたが――、「コロナは怖い! 宣言に従うのは当然!」という反応が圧倒的でした。
対して2回目(2021年1月~3月)では、「宣言を出す前に、1回目の宣言は本当に効果があったのか。やり過ぎだった部分がないのかを検証すべきだ」という声がそこそこ上がった。だから僕はむしろ、「お、ここから日本人も『議論』を始めるのでは?」と少し期待していたんです。
ところが3回目(2021年4月~6月)の宣言では、民意がもはや「この宣言は本当に妥当なのか? しっかり議論しよう」というフェーズを飛び越えて、「つきあいきれねーから、黙って無視しようぜ」という感じになっています(笑)。まさに「議論しない日本人」「議論できない日本人」を象徴するようでした。
浜崎 正確に言っておくと、僕は1回目の冒頭から反対したのではなく、「4月末まで」と言われていたのが、「5月も続けます」と延長されたところで、反対の声を上げたんです。まずは、編集委員を務める『表現者クライテリオン』のメールマガジンで、その後は、雑誌や新聞のコラムで「過剰自粛」批判を書き続けました。
2回目の緊急事態宣言の時も、世間の空気が「自粛」の方に流れていたので、緊急事態宣言に対する疑問を書いたのですが、ただ、3回目以降は、あまり書かなくなりましたね。単に呆れたということもありますが、與那覇さんがおっしゃったように、世間が宣言を「無視」しだしたので、わざわざ言うまでもないかなと(笑)。
與那覇 1回目の宣言の最中には「非国民」のように言われた我々の感覚が、いまやむしろ国民の多数派になっていますからね(苦笑)。
知性がないことがバレた大学教授
浜崎 ということもあって、その頃から批判の優先順位を変えて、対面授業を行なっている小中高に対して、大した根拠もなくリモート授業を続ける大学を批判しはじめることになります。学生のことを考えると、そこが緊急を要する論点だろうと。
しかし、普段は「議論が大事だ」と言っている「知性主義者」ほど、コロナに関しては「議論」を拒否して、「自粛」に固着しましたね。その点、「知性があれば議論ができて、反知性主義者は議論ができない」という彼らの嘘がバレました。

浜崎洋介氏 ©文藝春秋
確かに「議論」に「知性」は必要ですが、しかし、その前提には、互いに「主体」として認め合っている共同性がまず必要なんですよ。その共同性が人の「心理」や「感情」を支えているという事実があるわけですが、それらを軽視してきた「知性主義者」ほど、今回のコロナ禍では、「心理」や「感情」に足をすくわれたように見えます。
與那覇 「大学の先生は浮世離れしているかもしれないけど、でもその分、世俗から一歩距離をとって冷静に思索できる人なんだ」という、知性主義の幻想は崩壊しましたね。彼らの圧倒的多数は、「実のところは大衆(民意)に迎合しきっているのに、単に売れてない人」でしかないと見抜かれちゃった。
浜崎 実は、それで思い出すのが、大学のゼミでの議論です。ゼミでは、「保守」とか「リベラル」といった思想的・政治的立場に関係なく、学生たちに何でも自由に「議論」してもらうことを心がけているんですが、そこで、渋谷でのハロウィンパーティーが話題になったことがあったんです。
それで僕が「ああいう騒ぎ方はどうなのか? 孤立感をまぎらわすだけの刹那的な快楽主義にしか見えない」と言うと、ある「意識の高い」男子学生が、「先生、それは違う。価値観は人それぞれだから、別にいいと思いますよ」と。そこで僕が、「なるほど、じゃあ、僕の言う『あの騒ぎ方は不快だ』というのも一つの価値観なわけだよね」と問うと、「いや、違います。価値観は多様だからハロウィンパーティーがあってもいい」と。
こういう堂々めぐりを3回くらい繰り返して、最後は「ふざけんな!」となったんですが(笑)、要するに、「議論」するには、「知性」より以前に、相手の言ったことは無視しないとか、そういう当たり前の作法が必要なんですよ(笑)。「相手に自分を開こう」という他者への「信頼感」が「議論」の前提としてあるということです。
でも、それこそ「気持ちの余裕」から生まれるもので、自分が「安心」できないうちは、やっぱり他者に自分を開くのは難しい。
與那覇 「コロナは怖い!」という不安に囚われてしまった瞬間、「海外と比べたとき、日本の感染者数や死亡率は全然低いんですよ」という数値を示されても、冷静に見れなくなってしまう。自分が感じる恐怖感に沿ったデータしか、頭に入ってこなくなるということですね。
浜崎 おっしゃる通りです。現在(6月11日)、緊急事態宣言下にある東京の病床使用率は3割程度です。医療逼迫が深刻だった大阪はやむを得なかったとしても、東京を宣言の対象にする必要はあるのか。なぜ3割程度で「緊急事態」なのか。しかし、こう口にしただけで、「お前は人を殺す気か!」と言われてしまう。
議論のポイントは「自分を開く」姿勢
與那覇 先ほどおっしゃった「相手に自分を開く」というのは、すごくいい言葉だと思うんです。つまり自分の意見はあっても、「違う意見でも聞くよ」とか、「聞いた上で、自分の意見が変わることもあるかもしれない」といった態度ですね。
「俺は正義の側にいる。よって悪には屈しない!」といった態度の人は、そもそも自分を開いていない。その点でいうと、特定の思想や宗教へのコミットが弱い日本人って、本来は「開かれている」人が多かったんじゃないかと思うんです。ただし、それが「議論」という形をとらない点に問題がある。

與那覇氏による近著『平成史――昨日の世界のすべて』書影
たとえばですけど、その「ハロウィンは多様性だ」の学生に対しては、ゼミの後の飲み会でフォローとかはしたんですか?
浜崎 ちゃんと飲みに行って、丁寧に揉んであげましたよ(笑)。
與那覇 ゼミや職場の公式の会議では、まったく自分の意見を変えず「開かれない」。しかしその後の酒席では、ざっくばらんに打ち解けて「開かれる」人というのは、大人にも結構いますよね。そういう「開かれ方」が、日本人の特殊性かもしれません。
浜崎 ゼミでは開かれなくとも、飲み会では開かれるのは、飲み会の場には、一つの「共同性」があるからですよね。「自分はここの場所にいていい、受け入れられている」という安心感。ゼミの場は、どうしても成績(単位)のために集まっているというよそよそしさがあり、「言うと浮いちゃうかな」とか、「カッコつけなきゃ」という自意識が拭えないんですが、飲み会では、目的から解放された安心感がある。
與那覇 なるほど。「優秀なメンバー」を演じないと周囲から敬意を持たれないような人間関係と、「単なる飲んだくれ」でも別にええやないかと互いに思える人間関係との違いが、効いてくるわけですね。
浜崎 それで言うと、エーリッヒ・フロムが『愛するということ』(紀伊國屋書店)のなかで言っているのもそれで、フロムが言う「善」というのは、「他者とカップリングする力」のことなんですよ。他人を愛し「安心」をつくる力です。だから、その反対の「悪」は、他者との共同性を破壊する力、「孤立」と「不安」を誘うネガティブな力だということになる。
でも、そうなると、人間は「孤立」を回避することに必死になって、「議論」どころではなくなってしまうんです。そして、三つの回避案に向かっていく。
1つ目は、「祝祭的興奮」。前近代ならお祭りなんでしょうが、近代以降は、アルコールやドラッグやセックス依存など、「刹那的快楽に逃げる」ことになります。
2つ目は、「集団への同調」です。前近代なら、自他を超えた「伝統」があったんでしょうが、近代以降は、単なる画一主義に向かう傾向が強くなります。
3つ目は、「仕事」。「創造的な仕事に打ち込むことから生まれるやりがい」です。でも、これも近代以降は、単なる取り換え可能な「労働」になりつつあります。
與那覇 フロムの専門は社会心理学で、『自由からの逃走』(東京創元社)というファシズム分析でも知られています。たとえばナチズム下のドイツが採用したのは第2のアプローチで、「俺はこの党の一員だ!」という画一的な一体感を国民に与えることで、「孤立」を解消させていた。
浜崎 その通りです。そして、その究極版が、「支配と服従の全体主義」なんですね。フロムは、それを「サド/マゾ」関係に例えるんですが、要するに、サド(支配者)は、服従者を自らの一部に取り込むことで、自分の孤立感を癒やし、マゾ(服従者)は、支配者の一部になりきることによって、自らの孤独感を癒やすんです。

浜崎氏による近著『三島由紀夫――なぜ、死んでみせねばならなかったのか』書影
與那覇 DV(家庭内暴力)などでも、被害者の側が殴られることに「相手から必要とされている」といった生きがいを見出してしまうと、むしろそこから抜けられなくなってしまうんだそうですね。
浜崎 その意味で言えば、コロナの「同調圧力」を利用してサディスティックに振る舞っている小池百合子東京都知事も、どこか「孤独」に見えませんか(笑)。
與那覇 彼女は「旬」な政治勢力を軽やかに渡り歩いてきたようでいて、大宅賞を受賞した石井妙子さんのノンフィクション『女帝 小池百合子』(文藝春秋)を読むと、むしろこれほど一貫して「孤独な政治家」がいるのかと感じますよ。
なぜ「居酒屋自粛」は危険なのか
浜崎 ただ「孤立」しているのは、僕らも同じであって、この約30年間、新自由主義によって共同体や中間団体は掘り崩され、人々はますます「孤立感」を抱えるようになっています。そこにコロナ自粛の不安が加わって、さらに「孤立感」が深まっている。
ということは、「孤立」を脱したいという潜在的欲求も高まっているはずで、それが悪い形で発揮されれば、「支配と服従の全体主義」の呼び水になる可能性もあります。実際、オリンピックは、「祝祭的興奮」のために利用されていますよね。
その点、いま、僕がとくに問題だと思うのは、「自粛」によって、社会学用語で言うところの「サードプレイス(第3の場所)」が潰されていることです。
「ファーストプレイス(第1の場所)」としての自宅や、「セカンドプレイス(第2の場所)」としての職場や学校とは違って、「サードプレイス(第3の場所)」というのは、要するに、目的なしで集まれる「居酒屋」のような場所ですね。
與那覇 そこがまさに「自粛の標的」にされていると。つまり「別に目的もなく来ていた場所なら、閉鎖してもいいだろ?」という風に扱われてしまう。
浜崎 そこが標的になると、まさに「不要不急」によって他者と社交していく場所が潰されることになるわけですから、人々の「孤立感」は深まっていく一方です。
與那覇 そもそも「飲食店が感染拡大の主因だ」というエビデンスを、1回も政府は示していない。「酒の提供をやめるのが対策だ」とか言ってる専門家は、ドリンクバー付きのファミレスに行ったことがないんでしょうね。ソフトドリンクだけで中高生や地元の高齢者が、毎日何時間も喋りまくってることすら把握してない(苦笑)。
3回目の宣言ではなぜか、「百貨店も高級品売場は閉めてください」ということになりました。しかし高級品売場っていつも人っ気がなくガラガラで、ただし稀に来る客が1回に数十万~百万円単位のお金を落とすから、ペイしてますという世界でしょう? 地上で最も「密」から遠い業態なのに、そこを閉めるのが対策だという。
浜崎 そういう当たり前の「常識」すら通用しなくなっていますね。
與那覇 ぶっちゃけた話、政府や専門家にとってもウイルスなんかどうでもよくて、ウイルスの流行によって人々が溜め込んだ「ストレス」の方が怖いんでしょう。その矛先が自分に向かないように、「いやいやみなさん、叩くなら『飲んでるやつ・贅沢してるやつ』の方を叩いてください!」と必死に誘導している(失笑)。
「感染症対策」の仮面を被って、「感染症とはまったく関係のない何か」が社会を覆っている感じがします。

飲食店での「飲み会」を自粛し、帰宅するよう呼びかける区の職員ら
浜崎 「政治的に企図されたもの」というより一種の「集団ヒステリー」なんでしょうが、意識的なものではないだけに余計に厄介です。この閉塞状況を打ち破るには、堂々と飲んで、「安心」して見せるしかない(笑)。
飲み会だけでは「議論」にならない
與那覇 僕も、飲み会的な場所で生まれる「信頼感」や「精神的なゆとり」こそが社会に不可欠だと思って、1回目の宣言下からずっと「不要不急の外食はやめましょう」といった自粛には反対してきました。
しかし一方で考えないといけないのは、「飲み会でのおしゃべり」が本当に「議論」につながるのかという問題です。
浜崎 「おしゃべり」自体は、「議論」とは違いますからね。
與那覇 民俗学者だった宮本常一の『忘れられた日本人』(岩波文庫)の冒頭に、有名な「対馬の寄合」の話が入っています。フィールドワークに来たヨソ者の宮本さんに「村の古文書を見せてあげてもいいか」を、どうやって決めるかというと、夜通し飲みながらあーだこーだ話しあって、みんなが疲れてきたあたりで「ここまで話しあったんだし、いいじゃないの」的にOKを出すんだと。
宮本常一は、これを「日本的な意思決定のあり方」として捉えています。こうした寄合では、酔いつぶれるやつ・寝るやつ・途中で帰るやつ……がいて、誰も話を全部は聞いてないし(苦笑)、そもそも脱線や雑談だらけ。しかしだからこそ、とりあえず「みんなで決めた」「俺だけが無視はされなかった」という感覚は残るし、意見がぶつかった人と翌朝顔を合わせても、気まずい思いをしないですむと。
これはこれで確かに、長年同じメンツで暮らす村社会でも「なかよく」やっていく上では、合理的な慣行ではあった。しかし一方で、それって「議論なんですか?」と言われれば、そうではないですよね。
浜崎 そこは、それぞれの社会の文化背景を考える必要がありますよね。
例えば、ピューリタニズムの伝統が強いアメリカは、共同体から孤立しても、神とユニットを組むことで「自分を立てる」ことができる。それが、アメリカが、8~9割の人が何らかの神を信じていると言われるほどの宗教国家であるゆえんです。
ヨーロッパでは、信仰を持っている人は3割程度で少ないんですが、その代わり、キリスト教は「文化」としての存在感を持っているし、個人を支える国家の力も強い。エマニュエル・トッドも強調していますが、ヨーロッパの「個人主義」は、実は「国家主義」によって支えられているんです。個人と国家は対立するものではなく、相補的に組み合って、大きな国家の公共福祉によって個人も自立できるんですね。
で、中国はと言えば、まさに與那覇さんが『中国化する日本』(文春文庫)で書かれているように、「血縁」を重視する「宗族システム」がある。どんなに落ちこぼれた個人でも、「宗族」に寄食すれば、何とか食いっぱぐれることはないだろうと。

與那覇潤氏著『中国化する日本 増補版 日中「文明の衝突」』
「神」とユニットを組むアメリカ、「国家」や「文化」とユニットを組むヨーロッパ、そして、「宗族」とユニットを組む中国。それらに対し、日本はどうなのか。日本人がユニットを組むのは、「地縁」で、要するに「地域共同体」なんですよ。
與那覇 おっしゃる通りで、江戸時代には檀家制度が徹底されたから、形式的には日本人はみな仏教徒になったわけですが、結果としてヨーロッパに先んじて宗教の形骸化が進みました。要するに「冠婚葬祭や、地域の集まりごとに場所を提供する」のがお寺の役割になって、近代以降の市役所や公民館と変わらなくなった。
一方で村の内側で生活が完結したから、江戸時代は庶民にとって、日本全土を統一する「国家」の存在感は稀薄でしたね。そうしたあり方は、コロナワクチンの接種も地元の自治体に丸投げで、政府が直接管掌できない今日まで続いています。
浜崎 だから日本は、ヨーロッパよりも国家が強くないんですが、ということは、「地域共同体」や「中間団体」が崩れた時に一番弱いのは日本人だと言うことにもなりかねない。残りの手札は、サードプレイスとしての居酒屋くらいしかない(笑)。
事実、歴史学者の阿部謹也は、「日本人の生活を支配し、日本の特異性をつくってきたのは『世間』だ」と言っていますが(『「世間」とは何か』講談社現代新書)、僕自身もマンションの理事長を務めた時に、まさに宮本常一が描いているような「日本型合意形成」を経験しましたよ(笑)。理事のなかで一番若かったので、「こんな若いやつに任せて大丈夫なのか?」と、お爺ちゃん、お婆ちゃんが絡んできて本当に面倒だったんですが、結局、会議室を借りて、皆で飲むしかなくなるんですよ(笑)。
與那覇 21世紀に入っても、「村の寄合」をマンションでやるわけですね!
浜崎 そう、現代の東京23区内の都会でも、対馬の「寄合」と同じで、2、3時間も飲みながら話すと、「ここまで飲んだんだから、あんた信頼するわ」となって(笑)。
「わきまえない」ことはマイナスなのか?
與那覇 今年2月に森喜朗さんが失言で五輪の責任者を外れることになり、彼が口にした「わきまえる」という言葉が逆に流行したりしました(笑)。飲み会的な交流を通じて生まれる信頼感は、確かに相互に自分を「開いていく」ことにつながる。ただ、それは議論して結論を出すというよりも、互いに「わきまえましょうよ」と、そういう方向に作用していくわけですね。

東京五輪組織委員会会長を辞任した森喜朗氏 ©文藝春秋
浜崎 確かに、そうした流れになりがちですよね。
與那覇 結果として、いまの日本では奇妙なことが起きていると思うんですよ。
まず一方の極に森さん的、村の寄合的な「わきまえる」関係を自明視して暮らす人たちがいる。彼らは、飲み会でだらだらやれば「最後は一つにまとまる」と思っているので、飲んだ後でも違う意見を主張し続ける人を「わきまえないやつだ」として叩いてしまう。これでは、異なる意見どうしの議論は育たない。
ところがもう一方に、前者への苛立ちから「進んだ欧米ではこうなんです。これがグローバルエリートがもう出している正解で、世界標準と違う日本人はオカシイ!」と決め込んでしまう人たちがいますね。どことは言わないけど意識高い系のネットメディアと、大学に多い(笑)。しかしこれもこれで、最初からひとつの答えを決め打ちするだけだから、やっぱり議論にはつながらない。
いわば「日本の伝統派」と「欧米の最先端派」の双方が、それぞれ別のやり方で「異なる意見を発信しやすい社会」を潰している。そうした構図があるような。
浜崎 『歴史なき時代に』(朝日新書)で、與那覇さんは、「どんな人であれ他の誰かに依存しながら生きていく。ただし、その依存のしかたには良し悪しがある。〔……〕鍵になるのはやはり主体性。本人の主体性を賦活して、自立の方向へと徐々に傾けていく、そうした再出発のための安心できる『基地』としてなにかに依存するのは、ポジティヴだから大いにありだと思う」と書かれていますね。繰り返すようで恐縮ですが、やっぱり、この「安心できる基地」というのが鍵になるんじゃないかと。
「叩かれたくない」と怯えて自分に閉じこもるのではなく、「叩かれてもいい」と踏み出して議論できるのは、それ以前に、「自分自身を無条件で承認してくれる場所=安心できる基地」がどこかにあるからですよね。それが必ずしも物理的な場所である必要はないですが、その「基地」が多いほど、自由に「議論」が展開できる。
実際、歴史を振り返ってみれば、冷戦下の左右の対立が激しい時期でも、今よりは、よほど「議論」は自由だったし、主体性もあったように思うんですよ。
與那覇 「この人たちだけは何があっても、自分の味方になってくれる」という安心感があるからこそ、敵対する側ともそれなりに付き合えた面がある。「どうにもお互いわかりあえませんが、しかし、それぞれに支持者がいるんですから」と。
しかしいまは左右対立の構図が崩れた分、論点ごとに誰が敵で誰が味方か、目まぐるしく入れ替わり続けるような状態です。だから安心できる基地がなく、あらゆる争点で「俺が潰されるか、お前をブッ潰すかの二択だ!」となってしまう。
有料会員になると、この記事の続きをお読みいただけます。
記事もオンライン番組もすべて見放題
新規登録は「月あたり450円」から
-
1カ月プラン
新規登録は50%オフ
初月は1,200円
600円 / 月(税込)
※2カ月目以降は通常価格1,200円(税込)で自動更新となります。
-
オススメ
1年プラン
新規登録は50%オフ
900円 / 月
450円 / 月(税込)
初回特別価格5,400円 / 年(税込)
※1年分一括のお支払いとなります。2年目以降は通常価格10,800円(税込)で自動更新となります。

有料会員になると…
日本を代表する各界の著名人がホンネを語る
創刊100年の雑誌「文藝春秋」の全記事、全オンライン番組が見放題!
- 最新記事が発売前に読める
- 毎月10本配信のオンライン番組が視聴可能
- 編集長による記事解説ニュースレターを配信
- 過去10年6,000本以上の記事アーカイブが読み放題
- 電子版オリジナル記事が読める
source : 文藝春秋 電子版オリジナル













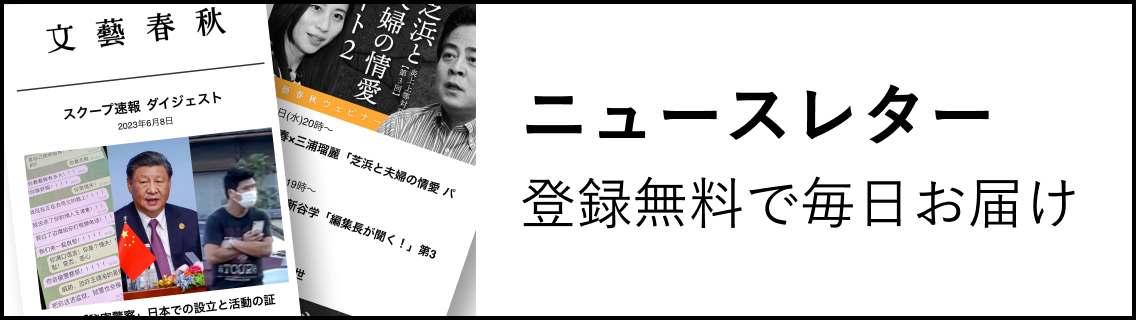
 トップページ
トップページ 後で読む・閲覧履歴
後で読む・閲覧履歴 マイページ
マイページ