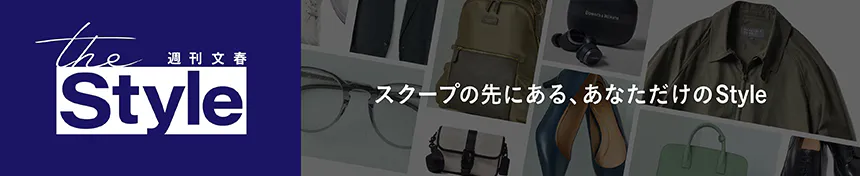3月8日、『新劇場版』シリーズ完結編である『シン・エヴァンゲリオン劇場版』がついに全国公開された。コロナ禍の影響での延期を乗り越え、平日、しかも月曜日という公開日にも関わらず、初日興収8億円を記録。その後も公開21日間で興行収入60億を突破し、早くも前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』(2012年公開)の最終興収約53億円を超えるシリーズ最高記録となっている。
テレビシリーズ、その劇場版に続き3回目の結末を迎えた『エヴァンゲリオン』。本作について、アニメ評論家の藤津亮太氏が語った(本文では劇中の内容に触れています。ご注意ください)。
◆◆◆
映画監督の黒沢清は、「世間が思ういわゆる“映画”」について、「『見せる』スペクタクルと『感銘させる』人間ドラマ」の融合である、と結論づけている(『映画はおそろしい』所収の「人間なんかこわくない」)。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(以下『シン・エヴァ』)を見てまず思い出したのは、黒沢が記したこの「『見せる』スペクタクルと『感銘させる』人間ドラマ」という2つの要素で考える視点だった。
『エヴァンゲリオン』シリーズの2本柱と「人類補完計画」
というのも、私見を記すなら、『エヴァンゲリオン』シリーズは、「スケールの大きなビジュアル」と「個人のアイデンティティをめぐる内的葛藤」という両極端な要素を2本柱として出来上がっている作品と受け止めているからだ。
庵野秀明総監督は黒沢ほど“映画”というものに縛られていない演出家ではあるが、この『エヴァンゲリオン』シリーズの2本柱は、黒沢の指摘する「『見せる』スペクタクルと『感銘させる』人間ドラマ」と、偶然にもしっかり対応している。そして、このスペクタクルとドラマを絶妙にリンクさせる仕掛けとして、物語を牽引してきた「人類補完計画」が大きな役割を果たしている……。このような視点で、『エヴァンゲリオン』シリーズを見ると、観客として様々な発見があるように思う。
黒沢の文章はその「見せるスペクタクル」を取り上げて、こんなふうに続く。
「が、スペクタクルには基本的に金が掛かり、テレビジョンの出現以降、急速に困難の度合いを増す。だからこれに替わっていろいろなウリが試された。例えばセンス。確かに、時として抜群のセンスはどんなスペクタクルよりも『見せる』ことがある」
アニメもスペクタクルを描くにはそれなりのリソースが必要となる。おいそれとできるものではない。その点、1995年に始まった『新世紀エヴァンゲリオン』は、テレビシリーズという予算的制約の中で、スペクタクルを正面から描くシーンはなるべく絞り、むしろ「抜群のセンス」で見せていくことに注力した作品だったといえるだろう。
それがいちばんわかりやすく示されたのがタイポグラフィーで見せる演出だったし、それ以外にもかっこよく決まったレイアウトの止め絵や、それらをシャープな印象で見せる編集などが、「抜群のセンス」で『エヴァ』を支えていた。
よく知られている通り『エヴァ』は各話の平均作画枚数3500枚という予算的縛りの中で制作されていた。そういった外的要因を考慮に入れた上で第六話「決戦、第3新東京市」での使徒との戦闘は、止め絵を多く使うことのできる内容として設計されており、そこでは「スペクタクル」が「抜群のセンス」により、それとはわからない形でローカロリーな手法で表現されていたのである。