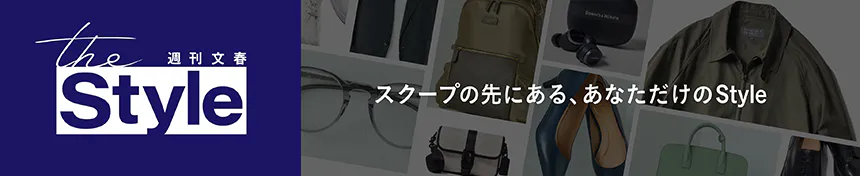この問題は根深く、実は父・善明さんも公正取引委員会に訴えることで、流通の一部改善にこぎつけた過去がある。善明さんの姿を間近で見てきた二村さんも泣き寝入りすることなく声を上げてきたものの、立場の弱い個人書店で後に続く人は少数で、孤独な闘いを強いられてきた。だから、「しんどい」。それでも、二村さんは書店を続ける道を選んだ。
「本を通じて作家さんにも、お客さんも会える。それが自分にとってはすごく嬉しいことなんですよね。本屋を辞めてビルを売ったら楽になるかもしれないけど、この喜びを失いたくないと思ったんです。私は本を通じて人と交流したいんだってわかりました」
今も変わらずこの思いを持ち続けているから、二村さんは今日も店頭に立つのだ。
リアル書店が生き残るヒントがここにある
2003年に2万880店舗あった書店は、2023年には1万918店舗に半減した(日本出版インフラセンターによる)。アマゾンの台頭、スマホの普及、電子書籍の登場などその背景にはさまざまな理由が考えられるが、隆祥館書店のお客さんの声を聞くと、「町の本屋さん」にもまだまだ可能性があると感じる。女性の常連客は、こう話す。
「大きな本屋さんは、新刊が並んでいて、そこから選ぶという感じなんですけど、隆祥館書店は、店長さんが『どんな本が好きですか?』『普段どんなことしてますか?』ってすごく親身に話を聞いてくださって。例えばその時に、『日本酒が好きです』と言ったら、『それならこの本は?』ってすぐに出てくるところがすごく楽しいんですよね。以前、自分では選ばないような本を勧めてくださって、最初は『こんな本読むかな』と思ったけど、読んでみたら面白かったんです。自分だけだったら選べなかった本と出会わせてもらってから、ここに通うようになりました」
このお客さんは、「仕事で疲れたなっていう時に寄りたくなるんです。ここで宝物を探すみたいな感じ」とほほ笑んだ。