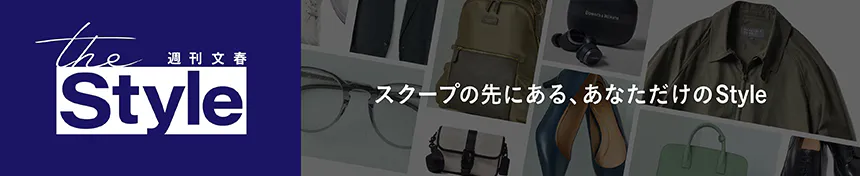地元・広島の自動車メーカー・マツダが筆頭株主になっている、プロ野球の人気球団「広島東洋カープ」。いまでこそ球界随一の「地域で愛されるチーム」だが、マツダもカープも、かつては苦難の連続だった——。
ここでは、日本経済新聞編集委員である安西巧氏の著書『マツダとカープ―松田ファミリーの100年史―』(新潮社)から一部を抜粋。マツダの前身である東洋工業が戦後に歩んだ道のりを紹介する。(全2回の1回目/後編に続く)
◆◆◆
戦後広島の希望だったマツダとカープ
言うまでもなく、広島の戦後は過酷な状況で始まった。
1945年8月6日、マリアナ諸島テニアン島から飛び立った米軍機B-29「エノラ・ゲイ」が投下した原子爆弾によって広島市では約7万人が即死し、その年だけで約14万人の命が失われた。
爆心地の周囲1・5キロ以内の家屋は全壊した。当時の広島市長、粟屋仙吉(1893~1945年)は爆心地から1・2キロ南方の市内水主町(現在の広島市中区加古町)にあった市長公舎で絶命。1944年2月に約34万3000人だった広島市の人口は、被爆から3カ月後の1945年11月には約13万7000人と6割強も減少してしまった。
原爆投下から2日後(1945年8月8日付)の米紙ワシントン・ポストは、マンハッタン計画(原爆開発計画)に参画していた米コロンビア大学教授のハロルド・ジェイコブソンが「今後70年間は、草木は勿論一切の生物は生息不可能である」と語ったと報じている。この「70年不毛説」(「75年」という説もあった)は、2~3カ月後には焼け跡に雑草が芽を出したことで早々に「誤報」であることが証明されたが、命からがら生き延びた人々も、家や職場、学校が焼け、市民生活は失われたままだった。
終戦から5年後の1950年当時でも、広島駅前には物価統制の目を搔い潜ったヤミ市が広がり、映画「仁義なき戦い」で描かれたようなヤクザ同士の縄張り争いや抗争が繰り返された。
また、市内中心部を流れる旧太田川(本川)沿いにはピーク時約1000戸に上ったといわれるバラック建て住宅の集落(通称「原爆スラム」)があり、原爆や戦争で行き場を失った人々がひっそり暮らしていた。
国有地を不法占拠した状態だったが、行政は事情を考慮して黙認し、1970年代末まで約30年間「原爆スラム」は存続した。
そんな戦後の広島で、人々に復興への希望をいち早く与えたのは、敗戦から1カ月後に三輪トラックの生産再開に動き始めた東洋工業であり、1950年のプロ野球の2リーグ分裂に伴う球団拡張(エクスパンション)で発足したカープ球団だった。