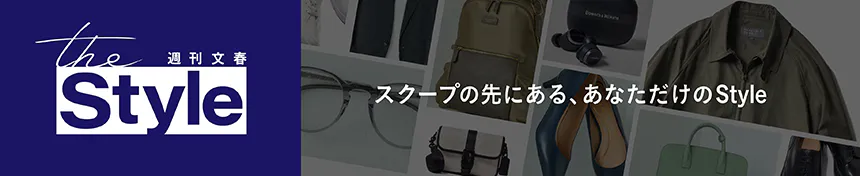日本で失われたはずの古代の糀の源流があった
――インド最果ての地にそんな村が?
小倉 僕も全く知りませんでしたが、日本ではとうに失われたはずの古代の糀の源流がそこでは温存されていた。もともと雲南省にルーツをもつメイテイ族は、数百年前にヒンドゥーの王朝の侵攻があったさい、一部の人々は改宗を拒み、森へと去りました。なぜなら、ヒンドゥー教においては醸造を「卑しい職能」とみなしますが、彼らにとって糀をつくり、酒をかもすのは先祖供養にかかわる尊い仕事だったからです。
あえてヒンドゥー秩序の外側に出て、「LOI」と呼ばれる不可触賤民として不当な扱いを受けながらも、醸造の伝統を捨てなかった誇り高き者――それが「森のメイテイ」と呼ばれる人々です。
その末裔がアジア最古の形の糀をつくり続けていた。インドで「LOI」には移動の自由も職業選択の自由も認められていません。ヒンドゥー社会の恩恵を一切受けられない境遇になってもなぜ糀をつくることにこだわったかというと、彼らはサナマヒ教という先祖崇拝の信仰をもっているからです。
詳しくは本書にゆずりますが、日本の神道とも共通点がいろいろあって、彼らは大事なお祭りのさい、お酒の最初の一杯を地面にこぼします。日本も春日大社とか古い神社では神様にお酒を捧げて地面にこぼします。そうやって土の中に眠っている先祖に対して敬意を示す。だから、森のメイテイは、先祖代々何百年も前から受け継がれてきた糀を大切に保存し、それを使って新しい酒をつくっている。
世界中の文献を探してもメイテイ族の生活・宗教にかんする研究はほとんどなくて、サナマヒ教と醸造の深い結びつきを明かした本書は、文化人類学的にも貴重な記録になったと自負しています。
アイデンティティと発酵の深い結びつき
――非常に意味の大きい旅になりましたね。
小倉 旅を振り返ってみて、日本人としての食文化のルーツが決して独立したものではなく、雲南省から北東インドに至る広大な“アジア発酵街道”に繋がっていることを実感しました。そこにはデタラメなものもいっぱいあって、アナーキーな食の面白さに満ちあふれていた。
今の僕たちの社会観って、とかく均質化へと向かいがちです。でもこの本に出てくる世界は、みんなが「こうやって世界は収斂していくんだろうな」と予測するものに1ミリも従っていない(笑)。ヒンドゥーや中華思想のような大きな秩序の外側で、全く別の世界観で生きている人たちです。そんな彼らのアイデンティティに発酵は深く結びついている。発酵食は本当にローカルな文化の塊だし 「持たざる者」の知恵の結晶ですから。
自由に生きることを貫くうえで、人は自分の感情だけを盾に大きな秩序に抗うのは難しいと思う。でも、祖先から引き継いだ固有の食の歴史を後ろ盾にすると、自分たちならではの自由を見つけやすくなる。発酵が自由への扉を開け放ってくれるんです。
INFORMATION
11月28日 【リアル&オンライン】小倉ヒラク✕高野秀行トークイベント
「発酵✕辺境!アナーキーな大冒険」
https://online.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-231128?variant=42753445167290
小倉ヒラク(おぐら・ひらく)
1983 年、東京都生まれ。発酵デザイナー。早稲田大学第一文学部で文化人類学を学び、在学中にフランスへ留学。東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、山梨県甲州市に発酵ラボをつくる。「見えない発酵菌の働きを、デザインを通してみえるようにする」ことを目指し、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマにしたプロジェクトを展開。絵本&アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014受賞。2020 年、発酵食品の専門店「発酵デパートメント」を東京・下北沢にオープン。著書に『発酵文化人類学』『日本発酵紀行』『オッス!食国 美味しいにっぽん』など。