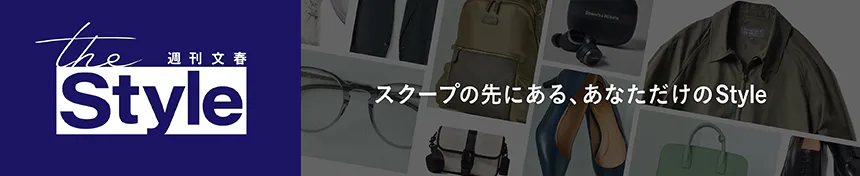編集者の指摘に「面倒くさいな」と思いながら……
――そうなんですか!? 西條さんの代表作といえば、今作もそうですが、直木賞を受賞した『心淋し川』など江戸の人情物語が印象的です。
西條 もともとは人情を書こうと思っていたわけではないんですよ。ストーリーを展開させていくことは割と得意だと思うのですが、むしろ感情の機微などを書くのは苦手だと思っていました。特にデビュー後5年くらいは、編集者の方に原稿をお送りすると、「もう少し感情の描写を膨らませてください」と言われていました。でも、どうもそのあたりにあまり興味が持てず、「面倒くさいな」と思いながら改稿していたのですが(笑)。そのおかげで小説の書き方を学べたのだと思います。
――そうでしたか……!
西條 どうしよう、読者の方をがっかりさせてしまったかも。
――いやいや、とても興味深いと思います(笑)。ところで、『初瀬屋の客』は江戸のお仕事小説とも言えますね。主人公の絵乃は公事宿「狸穴屋」で働き始めて3ヶ月。見習いを卒業し、一人前の手代として働き始めました。彼女も、そして宿の女将も「働く女性」。現代でこそ当たり前の光景ですが、当時は珍しかったのではないでしょうか。
西條 あえて「女将」という設定にしたのは、私が江戸でも現代でも、女性は手に職をつけている方がいいと思っているからです。特に子供がいる場合、経済的な事情を理由に離婚をしたくてもできない、などという不自由は味わいたくないですよね。
私自身、両親にそう教えられて育ったことも大きいかもしれません。特に父は「自立しろ」とうるさくて(笑)。
私、幼い頃はちょっと甘えん坊だったんですけれども、それを小学校1、2年の頃に担任教師が親に言ったらしいんですね。「ちょっと甘ったれのタイプですね」って。それを聞いた父が俄然張り切ってしまったみたい(笑)。父は両親を幼いころに亡くしていて、お姉さんたちに面倒を見てもらったそうなんです。「親はいつ死ぬかわからないから」と口を酸っぱくして言っていました。気づけば、私は作家なんて仕事をやっていますけど……。
逆に組織で働いていると、女性はどうしても出産や育児のために仕事を休まなければいけない時期があるじゃないですか。みなさん、それをどうやって乗り越えてるんだろうって。私にはできそうもないなと思っているので、両立されている方々の並々ならぬがんばりを思うと、素直に尊敬してしまいます。