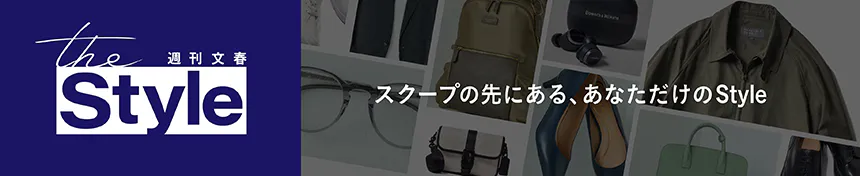大勢で集まって取り組む効果
読者の皆さんが二重課題運動を実践してみるなら、ウォーキングしながら簡単な計算やしりとり、川柳を作るといった認知課題に1セット30秒程度で取り組む方法が取り入れやすいでしょう。
アメリカのピッツバーグ大学の研究では、ウォーキングのような有酸素運動によって脳の記憶を司る海馬の容積が2%増加するとのこと。週3回のウォーキングを40〜50代なら40分以上、60代以上なら20分以上が目安だといいます。週3回以上の運動習慣を持つ高齢者は認知症になるリスクが低いとか、運動によって脳の神経細胞が増えるとする研究もあります。
一方、二重課題運動は、日常生活ではやらないことをやって脳に適度な負荷をかけることで脳の活性化を促します。体の運動であると同時に、脳の運動でもあるわけです。
ですからウォーキングに認知課題を組み合わせる二重課題運動は、通常のウォーキング以上に認知症予防効果が期待できるわけです。
もっとも、今後の検証が必要ではありますが、複数の人が教室で行う二重課題運動には、1人で行う運動にはない効果があると感じています。
大勢の人が集まって教室でやると、間違える人もしばしば出てきます。そのたびに「アハハ、間違えた」「いやー、難しいな」といった会話が自然と生まれます。
体を動かしながら笑顔でコミュニケーションすることは、認知症発症のリスク因子の「運動不足」だけでなく「社会的孤立」を回避するものでもあります。その点でも、先行研究のように黙々と行う運動にはないメリットがあると思うのです。
※ほかの項目も紹介した記事全文(約12,000字)は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」(古和久朋「脳を守る 世界標準の認知症予防法」)、及び「文藝春秋」2025年4月号に掲載されている。全文では下記の内容をご覧いただけます。
・卵は良い? 悪い? 食事で認知症予防
・脳の「老人斑」を解きほぐす
・モニタリングすべきは「睡眠時間」と「歩数」
・元「会社人間」は深刻 ソーシャルフレイルを超えろ