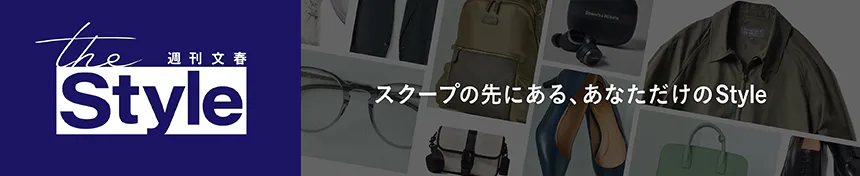漁港の朝市の「ことのおこり」をたどると…
勝浦は、歴史のある港町だ。
リアス式の海岸線で岩場が多く、沖合には黒潮が流れ、三方を囲われた天然の良港・三日月湾。これらが揃い、古くから好漁場として漁師町として栄えたという。
「勝浦」という町の名の由来も、諸説はあるがそのひとつに“勝れた浦”というものがあるくらい。記録に残らない時代でも、この地の人々は魚を捕って暮らしていたのだろう。
海に臨む突端の八幡岬には、勝浦城というお城もあった。戦国時代には、房総を領した里見氏の家臣・正木氏が居城とし、徳川家康が関東に入ると家康譜代の植村氏が入って城下町を整えた。
その頃には漁業のみならず、太平洋を介する海運の拠点になり、各地から物資が集まるようになっている。そうした事情を背景に、植村氏が勝浦に入って間もない1591年に始まったとされるのが、いまにも続く朝市である。
勝浦の朝市は、農産物と海産物の交換が目的の市だった。魚は豊富にあるが農産物には事欠く勝浦の人々が、それをうまいこと手に入れるための市、というわけだ。
上本町・仲本町・下本町というみっつの町を10日ごとに移動しながら365日毎日開かれていたという。江戸時代には、「勝浦三町江戸勝り」などと言われるほどに賑わったというから、なかなかである。
400年続く朝市の“現在の姿”
現在でも勝浦朝市は続いている。いまでは下本町と仲本町の2町体制で、月の半分ずつ場所を入れ替えて。そして、この市が開かれる港のすぐ脇の市街地が、いまも昔も勝浦の町の中心市街地なのである。
勝浦の中心市街地は、勝浦駅よりも港に近い。このあたり、この町が歴史的にも徹頭徹尾港町であったことを物語る。港の中心部付近から北東にまっすぐ伸びるのが仲本町通り。東側、遠見岬神社が鎮座する小高い丘沿いが下本町通り。両者は中央通りという商店街によって結ばれている。
訪れたのは昼下がり。だから朝市の賑わいなどはまったく感じられない。が、いまもって400年以上の歴史を持つ朝市と、そこに隣接する港町。これが勝浦という町の本質であり続けているということだけは間違いなさそうだ。