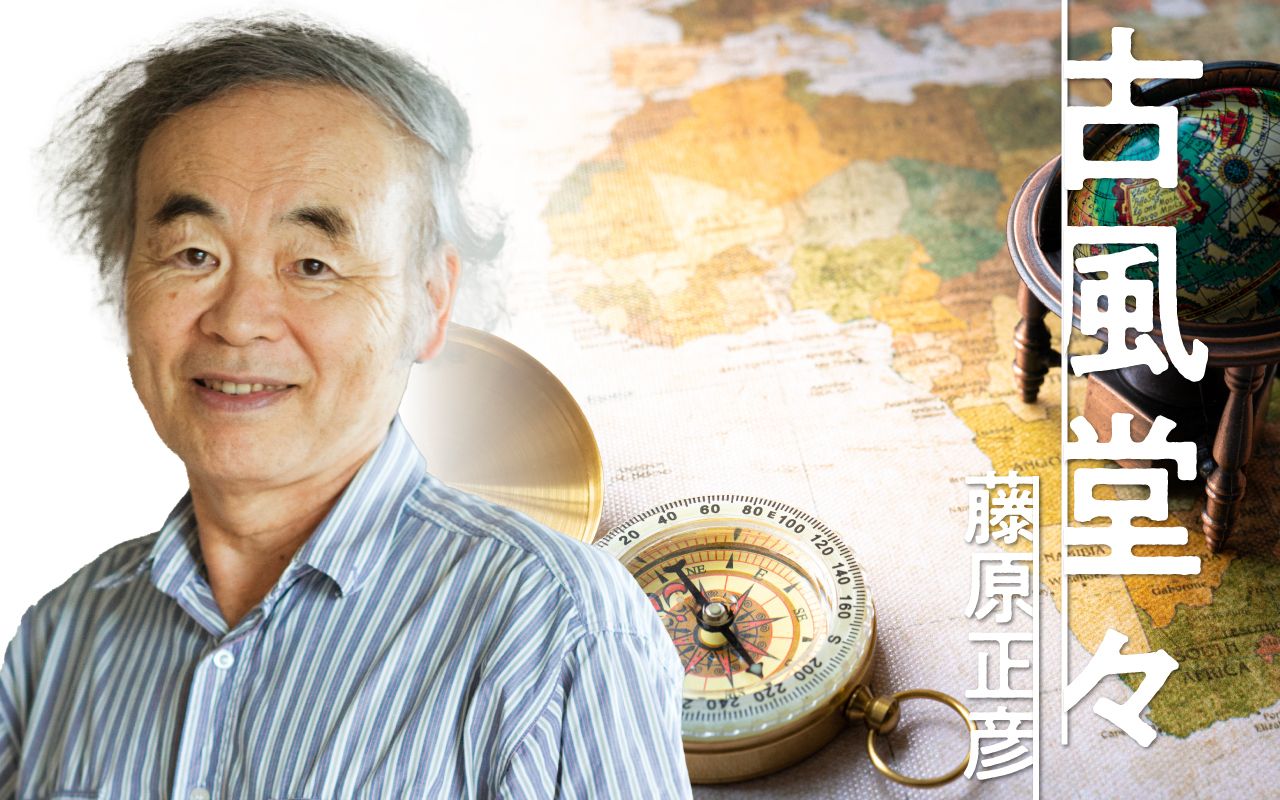
■連載「古風堂々」
第65回 内に静かに語りかけるもの
第66回 ふるさとの秋
第67回 神童の縦横無尽
第68回 言葉は時を超えて
第69回 新旧メディアに踊らされぬために
第70回 今回はこちら
在米経験の長いあるジャーナリストが以前こんなことを書いていた。「アメリカでは人物評価において次のことが重視される。(一)瞬発力がある(二)論理的に話せる(三)ユニークさがある(四)ネアカでユーモアセンスがある、の四つである」。三年間あちらに住んでいた私もそんなものと思う。ただ、同じアングロサクソンでも英国では少々異なる。瞬発力を発揮してまくし立てるような者は、「軽薄」とか「品がない」ととられる。論理をふりかざし主張するのは「フランス人のすること」と敬遠される。フランスでは政治家はもちろんタクシーの運転手までが口舌の徒である。論理など前提次第で結論はどうにでも変わる、自己正当化の道具にすぎない、と考える英国人は、論理より現実を重視し、抽象的な理屈をとうとうと述べるフランス人を胡散臭いと感じる。もっともフランス人の方は、英国人は現実を重視する余り、それまで述べた理屈を情勢しだいで平然とひっくり返す、と心からは信用していない。
ところがユーモアの大切さに関しては米英仏でさほど変わりない。ケンブリッジにいた頃、友人の数学者に「英国紳士の最重要条件は」と尋ねたことがある。彼は少考の後、「ユーモア」と断言した。出自、マナー、教養、気品など、信州の山奥から出てきた私に欠けるものばかりかと思っていた私は意表をつかれた。ただ、数学では天才的だが数歩進むとスキップする、という変わった男の意見だからと、念の為その後三十人ほどの学者、政治家、経済人などに聞いてみた。皆が異口同音に賛意を表した。なるほど英国の大きな書店には必ず「ユーモア」というコーナーがあり、ユーモア小説などがぎっしり詰まっている。ドイツではそんなコーナーはどこにもなかった。中世ヨーロッパ大陸の教会では、笑いは「悪魔の表現」「愚かさのしるし」「神を冒涜するもの」などと言われていたらしい。ルネッサンスの頃から演劇や文学に見られるようになったが、近代になっても「真面目」でなるドイツでは、小説や演劇でさえ道徳的なものが主流であった。私もドイツ人にユーモアが通じず当惑したことが何度かある。
この点、ヨーロッパ大陸から離れていた英国ではユーモアが発達した。十四世紀に書かれた『カンタベリー物語』はユーモアだらけだし、十六世紀のシェイクスピアなど悲劇の中にさえ笑いがちりばめられている。ケンブリッジ大学クイーンズ校の学長宅に夫婦で招待された時、彼は皿の上げ下げに何度も台所へ立った。余りにかいがいしいので思わず「今日は女房もいるからそんなに働かないで欲しい」と言ったら、私の目を二秒ほど見てから大笑いした。デザートを食べながら彼が、「英国は経済や初等教育など日本に学ぶべきことが多いが、日本が英国から学ぶことが何かありますか」と尋ねてきた。一九八〇年代、英国経済は長い斜陽のもとにあり日本経済は世界で一人勝ちをしていた。私は「いかにして優雅に朽ちるか英国に学びたい」と答えた。彼は爆笑し止まらなかった。これ以降、彼や娘が東京の我が家に泊まりに来るなど家族ぐるみの交際が始まった。ユーモアは人間同士の距離を一気に縮めるのである。スコットランドの片田舎で私達が食べた料理がとても美味だったので、給仕に尋ねた。「イギリスのフランス料理はどこもまずかったがここは例外だ。シェフはどこの出身ですか」「シェットランド島です」「何だ羊だったのか」。シェットランドは最高級の羊毛の生産地として有名なのだ。給仕は笑い、奥のシェフも爆笑したとかで、私達にデザートをサービスしてくれた。
ユーモアは駄じゃれの類いから、辛辣な皮肉や風刺、ブラックユーモアまで多種多様である。これらを貫く精神は「いったん自らを状況の外に置く」という姿勢である。「対象にのめりこまず距離を置く」という余裕である。ユーモアを最も大切と考える英国では、「彼はユーモアに欠けている」とは非難の言葉である。よく英国人はこう皮肉る。「ドイツ人はどんな小さな過ちも犯さない。犯すのは最大の過ちだけだ」。確かに第一次大戦と第二次大戦を始め、ホロコーストを行い、大量移民導入で欧州を破壊したのは、ユーモアを忘れたドイツ人だった。安倍元首相がトランプ米大統領と肝胆相照らす仲となったのは、安倍氏の傑出した地政学的感覚ばかりではなく、その卓抜なユーモアもあったと思う。石破首相はニコリともせず相手を見すえて話すが、これではトランプ、プーチン、習近平など狂暴なライオンに一蹴されそうだ。
日本は世界に冠たるユーモア大国である。古くから落語、漫才、狂言があるし、講談や歌舞伎もユーモア満載だ。文学でのユーモアなら源氏物語や今昔物語にもあるし、絵画でも浮世絵などはユーモアのかたまりである。人々を笑わせ、そして考えさせる研究に与えられるイグ・ノーベル賞に昨年、武部貴則東京科学大教授が輝いたが、その功績は哺乳類がお尻から呼吸できることの発見であった。新生児など呼吸不全患者の救命に役立つというから大発見だ。お尻呼吸の受賞を知った好奇心の強い少年が、実際に試してみようと、尻を水面から出して水に潜ったら、いつもより三十秒も潜水時間が伸びたとか。日本は十八年連続の受賞で、受賞者数は日英が図抜けている。この二国の類い稀な独創性とユーモア精神を物語っている。我が国の政治家、外交官、商社マンなどは世界の場で、人間関係を円滑化する切札としてのユーモア、誇るべき日本の伝統を存分に発揮して欲しいものである。
有料会員になると、この記事の続きをお読みいただけます。
記事もオンライン番組もすべて見放題
初月300円で今すぐ新規登録!
初回登録は初月300円
月額プラン
初回登録は初月300円・1ヶ月更新
1,200円/月
初回登録は初月300円
※2カ月目以降は通常価格で自動更新となります。
年額プラン
10,800円一括払い・1年更新
900円/月
1年分一括のお支払いとなります。
※トートバッグ付き
電子版+雑誌プラン
18,000円一括払い・1年更新
1,500円/月
※1年分一括のお支払いとなります
※トートバッグ付き
有料会員になると…
日本を代表する各界の著名人がホンネを語る
創刊100年の雑誌「文藝春秋」の全記事が読み放題!
- 最新記事が発売前に読める
- 編集長による記事解説ニュースレターを配信
- 過去10年7,000本以上の記事アーカイブが読み放題
- 塩野七生・藤原正彦…「名物連載」も一気に読める
- 電子版オリジナル記事が読める
source : 文藝春秋 2025年3月号













 トップページ
トップページ 後で読む・閲覧履歴
後で読む・閲覧履歴 マイページ
マイページ